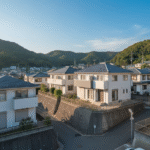一条工務店での家…

近年、日本各地で頻発する自然災害への備えは、家づくりにおいて最も重要な要素の一つとなっています。
特に、巨大地震に伴って発生する津波は、一瞬にして甚大な被害をもたらす可能性があります。
これからマイホームを検討される方の中には、積水ハウスの津波に対する性能や具体的な対策について、深く知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
積水ハウスは、東日本大震災において全壊・半壊ゼロという驚くべき実績を残しており、その高い耐震性には定評があります。
しかし、その強さの源泉である独自の制震システム「シーカス」や、建物を支える基礎構造、さらには鉄骨と木造(シャーウッド)の違いについて、詳しく理解している方は少ないかもしれません。
また、どれだけ頑丈な家を建てたとしても、土地の選定や設計の工夫なくして、津波のリスクを完全に払拭することは困難です。
この記事では、積水ハウスの津波への備えと、その背景にある優れた耐震技術について、多角的な視点から徹底的に解説します。
過去の災害実績から具体的な技術、そしてこれから家を建てる上で不可欠な防災対策まで、あなたの疑問や不安を解消するための一助となる情報を提供します。
fa-hand-pointer-o
この記事で分かる事、ポイント
- 積水ハウスが東日本大震災で全壊・半壊ゼロだった理由
- 独自の制震技術「シーカス」の仕組みと効果
- 建物の安全性を左右する基礎構造の重要性
- 鉄骨と木造(シャーウッド)の耐震性能の違い
- 津波リスクを避けるための土地選びのポイント
- 災害に強い家を実現するための具体的な設計手法
- 停電時にも役立つエネルギー自給自足設備のメリット
積水ハウスの津波への備えと耐震技術の実力
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 過去の震災で証明された全壊・半壊ゼロの実績
- 独自の制震システム「シーカス」の性能とは
- 基礎構造が支える積水ハウスの耐震性
- 鉄骨住宅と木造住宅シャーウッドの構造の違い
- 地盤調査から始める災害に強い家づくりの基本
過去の震災で証明された全壊・半壊ゼロの実績

積水ハウスの住宅が災害に対してどれほど強靭であるかを示す最も象徴的な事例が、2011年に発生した東日本大震災での実績です。
この未曾有の大災害において、津波による直接的な浸水被害を受けた地域を除き、地震の揺れが原因での全壊・半壊はゼロ件であったと報告されています。
これは、積水ハウスが長年にわたり培ってきた耐震技術の優位性を明確に証明するものであり、多くの人々に安心感を与えました。
マグニチュード9.0という観測史上最大の地震動に見舞われながらも、構造躯体に深刻な損傷がなかったという事実は、単なる偶然ではありません。
積水ハウスでは、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震など、過去の大地震の教訓を常に次の家づくりに活かしてきました。
実際の地震動を再現できる大規模な実験施設で、実物大の住宅を用いた振動実験を幾度となく繰り返し、構造体の強化や技術開発に努めてきたのです。
東日本大震災での実績は、こうした地道な研究開発と、一棟一棟の住宅に妥協なく注ぎ込まれた技術力の結晶と言えるでしょう。
家は、家族の命と財産を守るための最も重要な基盤です。
その基盤が、予測不能な巨大地震に対しても耐えうる強度を持つことは、何物にも代えがたい価値を持ちます。
積水ハウスが掲げる「安全・安心」という理念は、こうした過去の実績によって裏付けられているのです。
この実績は、これから家を建てる人々にとって、ハウスメーカーを選定する上での非常に重要な判断材料となるに違いありません。
独自の制震システム「シーカス」の性能とは
積水ハウスの優れた耐震性を語る上で欠かせないのが、独自の制震システム「シーカス(SHEQAS)」です。
これは、地震のエネルギーを効果的に吸収し、建物の揺れを大幅に低減させる画期的な技術です。
従来の「耐震構造」が、柱や梁を太くしたり壁を増やしたりして、建物を頑丈にすることで地震の力に「耐える」ことを目的としているのに対し、「制震構造」は揺れそのものを制御するというアプローチを取ります。
シーカスは、地震エネルギーを熱エネルギーに変換して吸収する特殊なダンパーを構造躯体に組み込んでいます。
地震が発生すると、このダンパーがしなやかに変形し、地震の力を受け流します。
これにより、建物の変形を最大で2分の1にまで抑えることが可能となり、構造躯体へのダメージを最小限に食い止めます。
さらに、繰り返し発生する余震に対しても、その性能を維持し続けることができる点も大きな特長です。
一度大きな揺れを経験した建物は、目に見えないダメージが蓄積している可能性があります。
シーカスは、本震だけでなく、それに続く数多くの余震からも建物を守り続けることで、住まいの資産価値を長期的に維持することに貢献します。
このシステムは、積水ハウスの鉄骨住宅はもちろん、木造住宅である「シャーウッド」にも標準で搭載されており、構造種別を問わず高い安全性を実現しています。
地震の揺れによる家具の転倒や破損のリスクも低減されるため、建物内部での二次災害を防ぐ効果も期待できます。
シーカスは、ただ地震に耐えるだけでなく、地震後も安心して暮らし続けることができる住まいを実現するための、積水ハウスの中核をなす技術なのです。
基礎構造が支える積水ハウスの耐震性

どれほど優れた構造体や制震システムを備えていても、それを支える「基礎」が強固でなければ、住宅の安全性は確保できません。
積水ハウスは、地面と建物を繋ぐ最も重要な部分である基礎構造にも、独自の技術と厳しい基準を設けています。
住宅の基礎には、主に「布基礎」と「ベタ基礎」の二種類がありますが、積水ハウスでは、地面全体を鉄筋コンクリートで覆う「ベタ基礎」を標準仕様として採用しています。
ベタ基礎は、建物の荷重を面全体で支えるため、力が分散されやすく、不同沈下(建物が不均等に沈み込む現象)を防ぐ効果が高いのが特徴です。
また、地面からの湿気やシロアリの侵入を防ぐ役割も果たします。
積水ハウスの基礎は、単にベタ基礎を採用しているだけではありません。
国の基準を上回る鉄筋量やコンクリート厚を確保し、構造計算に基づいて一棟ごとに最適な設計を行っています。
特に、外周部だけでなく、内部の壁下にも連続して基礎を設けることで、地震時に発生するねじれの力にも強い構造を実現しています。
さらに、基礎と構造体を緊結するアンカーボルトの数や配置にも細心の注意が払われており、地震の強い引き抜きの力から建物を守ります。
津波の際には、水の力だけでなく、漂流物が建物に衝突する衝撃も考慮しなければなりません。
強固な基礎と建物が一体化していることで、こうした外力に対しても家全体で抵抗することが可能になります。
見えない部分だからこそ、一切の妥協を許さない。
その姿勢が、積水ハウスの住宅の揺るぎない安全性を根底から支えているのです。
まさに、縁の下の力持ちとして、家族の暮らしを守り続けています。
鉄骨住宅と木造住宅シャーウッドの構造の違い
積水ハウスでは、主な構造として「鉄骨造」と、オリジナルの木造住宅である「シャーウッド」の二つを展開しています。
どちらの構造も、最高等級の耐震性を確保していますが、それぞれに異なる特性があり、どちらを選ぶかは個人の価値観や設計の自由度によって変わってきます。
まず、鉄骨造は、工場で生産された品質の安定した軽量鉄骨の柱や梁を、現場でボルト接合して組み上げる工法です。
部材の強度が高いため、柱の少ない広々とした空間や、大きな窓、ビルトインガレージといった、開放的な設計を得意とします。
鉄はしなやかで粘り強い性質を持つため、地震のエネルギーを吸収しやすく、変形しても倒壊しにくいというメリットがあります。
積水ハウスの鉄骨住宅では、前述の制震システム「シーカス」が組み込まれ、地震の揺れを効果的に制御します。
一方の「シャーウッド」は、木造でありながら、独自の「MJ(メタルジョイント)接合システム」により、柱や梁を強固に一体化させています。
従来、木造住宅の弱点とされてきた接合部の強度を飛躍的に高めることで、鉄骨造に匹敵するほどの耐震性を実現しました。
木の持つ温もりや調湿性といった特性を活かしながら、大開口や高い天井高など、木造の常識を超える設計の自由度も魅力です。
シャーウッドにもシーカスが標準搭載されており、木のしなやかさと制震技術が融合することで、優れた地震対応力を発揮します。
津波に対する直接的な抵抗力という観点では、構造の重量や剛性が高い鉄骨造に分があるという意見もありますが、どちらの構造も国の定める最高等級である「耐震等級3」を標準でクリアしています。
最終的には、どちらの構造が優れているかというよりも、それぞれのメリットを理解し、自身のライフスタイルやデザインの好みに合わせて選択することが重要です。
| 項目 | 鉄骨住宅 | 木造住宅(シャーウッド) |
|---|---|---|
| 主な特徴 | 軽量鉄骨の柱・梁。広々とした空間設計が得意。 | 独自のMJ接合システムで高強度を実現。木の質感が魅力。 |
| 耐震性 | 耐震等級3。制震システム「シーカス」標準搭載。 | 耐震等級3。制震システム「シーカス」標準搭載。 |
| 設計自由度 | 非常に高い。大開口、ビルトインガレージなど。 | 木造としては非常に高い。柱の少ない設計も可能。 |
| メリット | 品質が均一、しなやかで粘り強い、大空間の実現。 | 木の温もり、調湿性、独自の接合部による高強度。 |
地盤調査から始める災害に強い家づくりの基本

災害に強い家づくりは、建物の構造や性能を考える以前に、その家が建つ「地盤」を知ることから始まります。
どれだけ堅牢な建物を建てたとしても、足元である地盤が軟弱であれば、地震の際に液状化や不同沈下を引き起こし、建物に深刻なダメージを与える可能性があるからです。
積水ハウスでは、すべての建築予定地において、専門家による厳密な地盤調査を必ず実施しています。
この調査では、スウェーデン式サウンディング試験などの手法を用いて、地盤の硬さや土の種類、支持層の深さなどを詳細に分析します。
長年にわたって蓄積された膨大な地盤データと照合することで、その土地が持つ災害リスクを科学的に評価するのです。
調査の結果、地盤の強度が不足していると判断された場合には、決してそのまま建築を進めることはありません。
その土地の状況に最適な地盤改良工事を提案し、安全性が確認された上でなければ、基礎工事に着手しないという徹底した姿勢を貫いています。
地盤改良には、表層の土を固める方法や、地中にコンクリートの柱を築く方法など、様々な工法があります。
コストはかかりますが、これは家族の安全を守るために不可欠な投資と言えるでしょう。
特に、沿岸部や河川の近くなど、津波や洪水の被害が想定されるエリアでは、地盤の安定性がより一層重要になります。
強い水流に地盤が削り取られる「洗掘」のリスクも考慮しなければなりません。
積水ハウスでは、こうした地域特性も踏まえた上で、最適な基礎設計と、必要に応じた地盤改良をセットで考えることで、総合的な安全性を追求しています。
見えない地盤からこだわることこそが、真に災害に強い家づくりの第一歩なのです。
積水ハウスで津波を乗り越えるための家づくり
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- ハザードマップで確認すべき津波のリスク
- 津波被害を軽減する土地選びと設計の工夫
- 東日本大震災の教訓を活かした防災対策
- エネルギー自給自足で停電時も安心な設備
- まとめ:積水ハウスの津波対策で実現する安全な暮らし
ハザードマップで確認すべき津波のリスク

積水ハウスの津波に対する備えを考える上で、建物の性能と同等、あるいはそれ以上に重要なのが、建築予定地の立地条件です。
津波のリスクを正しく理解するためには、まず自治体が公表している「ハザードマップ」を確認することが不可欠です。
ハザードマップには、過去のデータやシミュレーションに基づき、津波が発生した際の浸水が想定される区域(浸水想定区域)や、予想される浸水の深さ(水深)が色分けで示されています。
これから土地を探す方は、このハザードマップを参考に、できるだけ浸水想定区域を避けて土地選びをすることが、最も基本的な津波対策となります。
すでに土地を所有している場合や、希望のエリアが浸水想定区域に含まれている場合には、そのリスクの程度を正確に把握することが重要です。
具体的には、「最大で何メートルの津波が到達する可能性があるのか」「浸水がどのくらいの時間継続するのか」といった情報を確認し、それに応じた対策を講じる必要があります。
積水ハウスでは、家づくりの相談段階で、こうしたハザードマップの情報に基づいたアドバイスも行っています。
専門的な知見を持つスタッフが、土地の持つリスクを評価し、安全な家づくりに向けた具体的な提案をしてくれるでしょう。
また、津波だけでなく、洪水や土砂災害、液状化のリスクなど、その土地が抱えるあらゆる災害の可能性を総合的に確認しておくことも大切です。
ハザードマップは、各自治体のウェブサイトや役所の窓口で簡単に入手できます。
家づくりという大きな決断をする前に、自分たちの住む場所の安全性を自らの目で確かめることから始めましょう。
津波被害を軽減する土地選びと設計の工夫
ハザードマップでリスクを確認した上で、やむを得ず浸水想定区域に家を建てる場合には、被害を最小限に抑えるための積極的な工夫が求められます。
積水ハウスでは、立地条件に合わせて、様々な設計上の対策を提案しています。
まず考えられるのが、敷地全体を盛り土したり、鉄筋コンクリートの擁壁を設けたりして、地盤の高さを上げる「かさ上げ」です。
これにより、津波の浸水を物理的に防ぐ、あるいは浸水深を浅くする効果が期待できます。
また、建物自体の基礎を高く設計する「高基礎」も有効な手段です。
1階の床面を周囲の地面よりも高くすることで、床上浸水を免れる可能性が高まります。
高基礎にした部分は、床下収納や駐車場として活用することも可能です。
間取りの工夫も非常に重要です。
例えば、寝室やリビングといった主要な居住空間を2階以上に配置する設計が考えられます。
万が一1階が浸水したとしても、家族が安全に垂直避難できる空間を確保しておくことは、命を守る上で極めて重要です。
さらに、電気の配電盤や給湯器といった重要な設備も、可能な限り高い位置に設置することで、浸水による故障を防ぎ、災害後の早期復旧に繋がります。
積水ハウスの設計士は、こうした津波対策に関するノウハウを豊富に持っています。
顧客の要望や土地の条件を丁寧にヒアリングしながら、安全性と居住性を両立させた最適なプランを提案してくれるでしょう。
建物の強さだけでなく、こうした多角的なアプローチによって、積水ハウスの津波への備えはより強固なものとなるのです。
東日本大震災の教訓を活かした防災対策

東日本大震災は、建物の耐震性だけでなく、災害後の生活をいかに維持するかという「在宅避難」の重要性も浮き彫りにしました。
積水ハウスでは、この教訓を活かし、建物が無事であった場合に、自宅で安全に過ごし続けるための様々な防災対策を提案しています。
その一つが、飲料水や食料の備蓄です。
津波の被害を受けた地域では、ライフラインの復旧に長い時間がかかることがあります。
積水ハウスの住宅は、大容量の床下収納やパントリーなど、備蓄品を効率的に保管できるスペースを確保しやすい設計になっています。
最低でも3日分、できれば1週間分の水と食料を備えておくことが推奨されています。
次に重要なのが、情報の確保です。
停電時でも情報を得られるように、電池式や手回し充電式のラジオは必需品です。
また、スマートフォンの充電が切れないように、モバイルバッテリーを複数用意しておくことも忘れてはなりません。
積水ハウスでは、コンセントの位置や数を工夫し、災害時にも使いやすい電源計画を提案しています。
さらに、家族との安否確認方法を事前に決めておくことも重要です。
災害用伝言ダイヤル(171)やSNSなどを活用し、複数の連絡手段を確保しておくことで、離れ離れになった場合でもお互いの無事を確認しやすくなります。
積水ハウスの「ファミリー スイート」のような大空間リビングは、災害時に近隣住民を一時的に受け入れる避難スペースとしても機能します。
頑丈な家は、自分たちの家族だけでなく、地域社会の安全にも貢献することができるのです。
こうしたハード面とソフト面の両方からのアプローチが、真の防災対策と言えるでしょう。
エネルギー自給自足で停電時も安心な設備
津波をはじめとする大規模災害が発生した際、最も深刻な問題の一つが長期間にわたる停電です。
電気が使えなくなると、照明や冷暖房はもちろん、調理や情報収集、通信手段までが絶たれ、避難生活の質は著しく低下します。
この問題に対する積水ハウスの答えが、太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせた「エネルギーの自給自足」です。
屋根に設置した太陽光パネルで発電した電気を、大容量の蓄電池に貯めておくことで、停電時でも自宅で電気を使い続けることが可能になります。
日中に発電して余った電気を蓄え、夜間や天候の悪い日に使用するというサイクルを確立すれば、電力会社からの供給が途絶えても、普段に近い生活を維持することができます。
積水ハウスの「グリーンファースト ゼロ」といった仕様では、これらの設備が標準的に搭載されており、平常時の光熱費削減に貢献するだけでなく、非常時には強力な防災設備として機能します。
蓄電池があれば、夜間でも照明をつけて安全に過ごせますし、冷蔵庫を稼働させて食料を保存することもできます。
また、テレビやスマートフォンから災害情報を入手し続けることができる安心感は、計り知れません。
さらに、電気自動車(EV)を所有している場合、それを「走る蓄電池」として活用するV2H(Vehicle to Home)システムも注目されています。
EVの大容量バッテリーから自宅へ給電することで、数日間にわたって電力を賄うことも可能です。
積水ハウスでは、こうした次世代のエネルギーシステムにも積極的に対応しています。
災害時にライフラインが寸断されても、自宅がエネルギーを自給自足できる安全なシェルターとなる。
これは、これからの家づくりにおける新しい常識となっていくでしょう。
まとめ:積水ハウスの津波対策で実現する安全な暮らし

これまで見てきたように、積水ハウスの津波への備えは、単一の技術に依存するものではなく、多層的かつ総合的なアプローチによって成り立っています。
まず、その根幹にあるのは、東日本大震災でも証明された圧倒的な耐震性能です。
独自の制震システム「シーカス」が地震の揺れを吸収し、国の基準を上回る強固な基礎と構造体が、巨大な外力から建物を守り抜きます。
鉄骨、木造(シャーウッド)といった構造の違いはあれど、どちらも最高の安全性を追求するという理念に揺るぎはありません。
しかし、積水ハウスの津波対策は、建物の強さだけに留まりません。
家を建てる前の地盤調査を徹底し、ハザードマップを活用して土地のリスクを顧客と共有することから始まります。
そして、浸水リスクを軽減するための「かさ上げ」や「高基礎」、居住空間を2階以上に設ける間取りの工夫など、立地条件に応じた最適な設計を提案します。
さらに、太陽光発電と蓄電池によるエネルギーの自給自足は、万が一の停電時にも自宅での生活を可能にし、家族に大きな安心をもたらします。
積水ハウスで家を建てるということは、単に頑丈な「箱」を手に入れることではありません。
土地選びから設計、設備、そして災害後の生活までを見据えた、包括的な安全ソリューションを選択するということです。
積水ハウスの津波への取り組みを深く理解することで、私たちは未来の災害に対して、より賢く、そして力強く備えることができるのです。
大切な家族との暮らしを、これからもずっと守り続けるために、信頼できるパートナーを選ぶことが何よりも重要と言えるでしょう。
fa-file-powerpoint-o
この記事のまとめ
- 積水ハウスは東日本大震災の揺れで全壊・半壊ゼロの実績
- 津波浸水地域を除き構造躯体の被害がなかった
- 独自の制震システム「シーカス」が揺れを最大半減させる
- シーカスは地震エネルギーを熱に変換して吸収する技術
- 国の基準を上回る強固なベタ基礎を標準で採用
- 鉄骨と木造(シャーウッド)の両方で最高の耐震等級3を実現
- 建築前に全棟で厳密な地盤調査を実施する
- 軟弱地盤の場合は最適な地盤改良工事を提案
- ハザードマップで津波リスクの確認を徹底
- 土地のかさ上げや高基礎設計で浸水被害を軽減
- 主要な居住空間を2階以上に配置する間取りを推奨
- 太陽光発電と蓄電池で停電時も電気が使える
- エネルギーの自給自足が災害時の在宅避難を支える
- 積水ハウスの津波対策は建物・土地・設備の総合力
- 家族の安全を守るための多角的なアプローチを提供