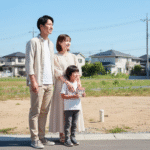注文住宅を建てる際、多くの人が夢見る理想の暮らし。その実現に欠かせない要素の一つが、日々の生活を快適にする「収納」です。
しかし、この注文住宅の収納計画は、意外と難しく、暮らし始めてから「こんなはずではなかった」と後悔するケースが少なくありません。
収納が足りない、あるいは多すぎた、場所が悪くて使いにくいといった失敗は、注文住宅づくりにおける大きな悩みの一つと言えるでしょう。
成功のコツは、ご自身のライフスタイルに合わせた最適な間取りを考え、実用的なアイデアを取り入れることです。
例えば、大容量で便利なファミリークローゼットや、食材のストックに役立つパントリー、アウトドア用品の収納に重宝する土間収納など、人気の設備を上手に活用することで、暮らしの質は格段に向上します。
この記事では、注文住宅の収納で後悔しないために知っておきたい計画の立て方から、おしゃれで機能的な収納の実例、気になる費用に至るまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。
これから家づくりを始める方が、収納に関する不安を解消し、理想の住まいを実現するための一助となれば幸いです。
fa-hand-pointer-o
この記事で分かる事、ポイント
- 注文住宅の収納計画でよくある後悔や失敗のパターン
- 収納計画を成功させるための具体的なコツと考え方
- 生活動線を意識した収納間取りの重要性
- すぐに取り入れられる便利な収納アイデアの数々
- ファミリークローゼットやパントリーなど人気収納の特徴
- 場所別の具体的な収納活用法とおしゃれな実例
- 収納スペースを設ける際の費用感と予算の考え方
◆
注文住宅の収納で後悔しないための計画術
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 収納計画でよくある後悔と失敗パターン
- 計画を成功に導くための5つのコツ
- 暮らしやすさを決める収納間取りの考え方
- すぐに真似できる便利な収納アイデア集
- 大容量で人気のファミリークローゼットとは
収納計画でよくある後悔と失敗パターン

注文住宅の収納計画は、家づくりにおける満足度を大きく左右する重要な要素です。
しかし、慎重に計画したつもりでも、実際に住み始めてから「もっとこうすれば良かった」という後悔の声が聞かれることは少なくありません。
ここでは、多くの方々が経験する典型的な後悔と失敗のパターンを具体的に見ていきましょう。
これらの事例を知ることで、ご自身の計画に潜むリスクを未然に防ぐことができるはずです。
収納量の失敗:少なすぎ・多すぎ問題
最も多い後悔の一つが、収納量の見積もりミスです。
「収納は多ければ多いほど良い」と考えがちですが、実際にはそうとも限りません。
もちろん、収納スペースが不足すれば、物が溢れてしまい、せっかくの新居が片付かない状態になってしまいます。
特に、子どもの成長や趣味の変化など、将来的な物の増減を考慮していなかった場合に、収納不足に陥りがちです。
一方で、収納スペースを過剰に設けてしまうと、その分、居住スペースや他の重要な空間が圧迫されてしまいます。
使われない収納スペースは、ただのデッドスペースとなり、建築費用の無駄遣いにもつながりかねません。
「とりあえず」で作った収納が、結果的に持て余すことになってしまうのです。
配置の失敗:生活動線に合わない
収納は量だけでなく、その「場所」が非常に重要です。
「使う場所の近くにしまう場所がある」という原則が守られていないと、日々の生活で大きなストレスを感じることになります。
例えば、洗濯物を干すバルコニーから遠い場所にファミリークローゼットを設けてしまうと、洗濯物を運ぶ手間が増えてしまいます。
また、キッチンで使う調理器具やストック食材をしまうパントリーが、調理スペースから離れていては、料理の効率が著しく低下するでしょう。
このように、生活動線や家事動線を無視した収納配置は、日々の小さな不便の積み重ねとなり、大きな後悔につながるのです。
設計の失敗:サイズや形状が不適切
収納スペースの内部設計も、使い勝手を決める大切なポイントです。
奥行きが深すぎるクローゼットは、奥の物が取り出しにくく、結果的に手前の物しか使わない「死蔵品」を生み出す原因となります。
逆に、浅すぎて収納したいものが収まらないというケースも考えられます。
また、棚の高さが固定されていて、収納したい物のサイズに合わない、コンセントがなくて充電式の掃除機を収納しながら充電できない、といった設計上の配慮不足もよくある失敗例です。
何をどこに、どのように収納したいのかを具体的にイメージせずに設計を進めてしまうと、使いにくい収納が出来上がってしまいます。
- 収納量が現在の持ち物や将来の増減に合っていない
- 収納の場所が生活動線や家事動線から外れている
- 収納内部の奥行きや棚の高さが収納物と一致しない
- 照明やコンセントがなく、暗くて不便な収納になっている
これらの失敗パターンを避けるためには、次の章で解説する「成功のコツ」をしっかりと押さえることが不可欠です。
自分たちの暮らしを具体的にシミュレーションし、細部までこだわって計画を進めていきましょう。
計画を成功に導くための5つのコツ
注文住宅の収納で後悔しないためには、計画段階での入念な準備と、暮らしに寄り添った視点が不可欠です。
ここでは、収納計画を成功させるために、ぜひ押さえておきたい5つの重要なコツをご紹介します。
これらのポイントを意識するだけで、計画の精度は格段に向上するでしょう。
1. 現在の持ち物をすべてリストアップする
まず、計画の第一歩として、現在所有している物をすべてリストアップすることから始めましょう。
衣類、本、食器、趣味の道具、季節用品、思い出の品など、カテゴリー別に分けて書き出していきます。
この作業は手間がかかりますが、自分たちがどれだけの物を持っているのかを客観的に把握するために非常に重要です。
リストアップする際には、サイズや量も大まかに記録しておくと、必要な収納スペースを計算する際に役立ちます。
同時に、この機会に持ち物の「断捨離」を行うこともおすすめします。
新居に本当に必要な物だけを持っていくことで、余分な収納スペースを計画する必要がなくなり、よりスマートな収納計画が可能になります。
2. 生活動線と家事動線をシミュレーションする
次に、新しい家での一日を具体的に想像し、家族の動き(生活動線)や家事の流れ(家事動線)をシミュレーションしてみましょう。
朝起きてから夜寝るまで、どこで何をするのか、物の出し入れはどこで発生するのかを考えます。
例えば、「帰宅後、コートを脱いでバッグを置き、どこで手を洗うか」「洗濯機を回し、干して、畳んで、しまうまでの流れはどうか」といった具体的な動きです。
このシミュレーションを通じて、「どこに」「何を」収納すれば最も効率的かが自ずと見えてきます。
「使う場所の近くに収納する」という原則を徹底することで、無駄な動きが減り、ストレスのない快適な暮らしが実現できるでしょう。
3. 将来のライフスタイルの変化を予測する
家は長く住む場所です。
現在の暮らしだけでなく、5年後、10年後、20年後のライフスタイルの変化を見据えた収納計画が求められます。
家族構成の変化は、物の量に最も大きな影響を与えます。
子どもの誕生や成長、独立など、将来の家族の姿を想像してみましょう。
子どものおもちゃや学用品、成長に伴う衣類の増加などを考慮しておく必要があります。
また、趣味や仕事の変化も物の増減に関わってきます。
将来的に増えるかもしれない趣味の道具や、在宅ワーク用の書類などを収納するスペースも考えておくと安心です。
可変性のある収納を計画するのも一つの手です。例えば、子ども部屋のクローゼットは、最初は広い一室として使い、将来的に二つに分けられるように棚やポールを可動式にしておく、といった工夫が考えられます。
4. 「見せる収納」と「隠す収納」を使い分ける
すべての物を扉の中に隠してしまうだけが収納ではありません。
「見せる収納」と「隠す収納」を上手に使い分けることで、空間におしゃれさと機能性をもたらすことができます。
「隠す収納」は、生活感が出やすい日用品や、あまり使わない季節物などをしまうのに適しています。
扉付きのクローゼットやパントリー、押し入れなどがこれにあたります。
空間をすっきりと見せることができるのが最大のメリットです。
一方、「見せる収納」は、お気に入りの雑貨や本、デザイン性の高い食器などをディスプレイするように収納する方法です。
オープンシェルフやニッチ(壁のくぼみ)などを活用します。
空間のアクセントとなり、自分らしさを表現できるだけでなく、よく使う物をサッと取り出せるという実用的なメリットもあります。
どこにどちらのタイプの収納を設けるか、バランスを考えて計画しましょう。
5. 設計士や専門家のアドバイスを積極的に活用する
自分たちだけで計画を進めるのには限界があります。
注文住宅のプロである設計士やハウスメーカーの担当者に、自分たちの要望やライフスタイルを詳細に伝え、積極的にアドバイスを求めましょう。
彼らは多くの家づくりの経験から、自分たちでは思いつかないような収納のアイデアや、動線を考慮した最適な配置を提案してくれます。
また、収納アドバイザーのような専門家に相談するのも有効な手段です。
持ち物の整理方法から、効率的な収納計画まで、専門的な視点から具体的な助言を得ることができます。
専門家の知識と経験を活用することで、計画の客観性が増し、より満足度の高い収納が実現できるでしょう。
暮らしやすさを決める収納間取りの考え方

注文住宅における収納計画は、単に物の置き場所を確保することではありません。
収納を間取りの一部として捉え、家全体の暮らしやすさをデザインするという視点が不可欠です。
ここでは、収納と間取りを一体で考え、快適な住環境を実現するための基本的な考え方について掘り下げていきます。
「収納率」に惑わされない
家づくりを検討していると、「収納率」という言葉を耳にすることがあります。
収納率とは、住宅の延床面積に対する収納面積の割合のことです。
一般的に、一戸建ての場合は12%〜15%程度が目安とされていますが、この数字はあくまで指標の一つに過ぎません。
重要なのは、収納率の高さではなく、その収納が自分たちのライフスタイルに合っているかどうかです。
例えば、アウトドアが趣味で道具が多い家族と、ミニマリストで持ち物が少ない家族では、必要な収納の量も種類も全く異なります。
数字に捉われるのではなく、前述の通り、まずは自分たちの持ち物を正確に把握し、必要な場所に、必要なだけの収納を計画することが肝心です。
ゾーニングで考える収納配置
家全体をいくつかのゾーンに分けて、それぞれのゾーンの役割に応じた収納を配置するという「ゾーニング」の考え方は非常に有効です。
一般的に、家は以下の3つのゾーンに大別できます。
- パブリックゾーン:リビング、ダイニング、キッチンなど、家族や来客が過ごす場所。
- プライベートゾーン:寝室、子ども部屋、書斎など、個人の空間。
- サービスゾーン:浴室、洗面所、トイレ、玄関など、家事や衛生に関わる場所。
パブリックゾーンでは、皆で使う物(本、DVD、ゲーム機など)や、来客用のアイテムを収納するスペースが必要です。
プライベートゾーンには、個人の衣類や趣味の物などをしまう収納が求められます。
サービスゾーンでは、タオルや洗剤、トイレットペーパーのストック、掃除用具などを効率的に収納する必要があります。
それぞれのゾーンで「誰が」「何を」「いつ」使うのかを考え、物の定位置を決めていくことで、家全体が整理され、使いやすい間取りになります。
回遊動線を意識したウォークスルー収納
近年、人気が高まっているのが「ウォークスルー」タイプの収納です。
これは、収納スペースを通り抜けられるように設計された間取りのことで、家事動線や生活動線をスムーズにする効果があります。
代表的な例をいくつかご紹介します。
- 玄関 → シューズクローク → パントリー → キッチン:買い物から帰宅した際の荷物の片付けが非常にスムーズになります。
- 洗面脱衣所 → ファミリークローゼット → 物干しスペース:洗濯の一連の作業(洗う→干す→しまう)が一か所で完結し、家事効率が劇的に向上します。
- 主寝室 → ウォークインクローゼット → 書斎:朝の身支度や、仕事への移行がスムーズに行えます。
このように、収納空間が動線の一部となることで、家の中をぐるぐると回遊でき、移動の無駄がなくなります。
ウォークスルー収納は、ただ物をしまう場所ではなく、暮らしに流れを生み出す機能的な空間として、間取り計画の際にぜひ検討したいアイデアです。
ただし、通り抜けのために通路分のスペースが必要になるため、ある程度の面積が求められる点には注意が必要です。
自分たちの暮らしにどのような回遊動線があれば便利になるか、じっくりと検討してみましょう。
すぐに真似できる便利な収納アイデア集
注文住宅の魅力は、既製品にはない自由な発想で、暮らしに合わせた工夫を凝らせる点にあります。
ここでは、デッドスペースを有効活用したり、少しの工夫で使い勝手を向上させたりする、すぐに真似できる便利な収納アイデアをご紹介します。
これらのアイデアをヒントに、ご自身の家づくりに役立ててください。
デッドスペースを収納に変える
家の中には、意識しないと見過ごしてしまう「デッドスペース」が意外と多く存在します。
これらの空間を収納として活用することで、居住スペースを圧迫することなく収納量を増やすことができます。
- 階段下収納:定番ですが、非常に有効なスペースです。掃除機や日用品のストック、子どものおもちゃ置き場などに最適です。棚を設置したり、引き出し式の収納を作ったりと、工夫次第で様々な使い方ができます。
- 壁面ニッチ:壁の厚みを利用して作るくぼみ収納「ニッチ」。スイッチ類をまとめたり、スマートフォンや鍵の置き場所にしたり、お気に入りの雑貨を飾るディスプレイスペースとしても活躍します。
- 床下収納:キッチンや洗面所によく設けられますが、リビングや廊下の床下にも設置可能です。長期保存できる食品や、普段あまり使わない調理器具、防災グッズなどの収納に適しています。
- 小屋裏・屋根裏収納:季節物の家電(扇風機やヒーター)、雛人形や五月人形、思い出の品など、年に数回しか出し入れしない物の収納場所として最適です。固定階段を設けると、荷物の出し入れが格段に楽になります。
これらのデッドスペースを活用することで、家全体がすっきりと片付き、空間を有効に使えるようになります。
造作家具で空間にフィットさせる
「造作家具」とは、その空間に合わせてオリジナルで製作する家具のことです。
注文住宅であれば、壁面にピッタリと収まるテレビボードや本棚、カウンター下の収納などを自由に設計できます。
造作家具の最大のメリットは、スペースに無駄なくフィットし、家全体に統一感が生まれることです。
市販の家具を置くとできてしまう微妙な隙間がなく、掃除がしやすいという利点もあります。
また、収納したい物のサイズや量に合わせて棚の高さや奥行きを決められるため、非常に機能的な収納を実現できます。
例えば、リビングの壁一面を収納棚にすれば、家族の写真や本、DVDなどをまとめて収納でき、空間の主役にもなります。
費用は市販の家具よりも高くなる傾向がありますが、長い目で見れば満足度の高い投資と言えるでしょう。
コンセントや照明計画も忘れずに
見落としがちですが、収納内部の設備計画も使い勝手を左右する重要なポイントです。
特に、以下の2点は計画段階で必ず検討しましょう。
- コンセントの設置:ウォークインクローゼットやパントリー、階段下収納などの内部にコンセントがあると非常に便利です。充電式の掃除機を収納しながら充電したり、除湿器を設置したり、DIY用の電動工具を充電したりと、用途は多岐にわたります。
- 照明の設置:奥行きのある収納や、窓のないウォークインクローゼットなどは、昼間でも暗くなりがちです。内部に照明を設置することで、奥の物まで見渡しやすくなり、探し物をするストレスがなくなります。人感センサー付きの照明にすれば、扉を開けるだけで自動的に点灯し、消し忘れの心配もありません。
これらのちょっとした配慮が、日々の暮らしの快適さを大きく向上させます。
「ここにコンセントがあれば」「ここが明るければ」と後悔しないように、収納スペースの利用シーンを具体的にイメージして計画に盛り込みましょう。
大容量で人気のファミリークローゼットとは

近年、注文住宅の収納計画において、採用を希望する方が増えているのが「ファミリークローゼット」です。
これは、家族全員の衣類などを一か所にまとめて収納するスタイルの大型クローゼットのことを指します。
ここでは、ファミリークローゼットのメリットとデメリット、そして計画する際のポイントについて詳しく解説します。
ファミリークローゼットのメリット
ファミリークローゼットが人気を集める理由は、その家事効率の良さと生活のしやすさにあります。
- 家事動線が劇的に短くなる:洗濯物を「畳んで、各部屋のクローゼットに運ぶ」という手間がなくなります。洗面脱衣所や物干しスペースの近くにファミリークローゼットを配置すれば、洗濯の一連の流れがその場で完結し、家事の負担を大幅に軽減できます。
- 朝の身支度がスムーズになる:家族全員の衣類が一か所にあるため、朝の忙しい時間帯でも、あちこちの部屋に行く必要がなく、効率的に身支度を整えることができます。クローゼット内で着替えが完結するような設計にすれば、リビングなどが散らかるのを防げます。
- 各部屋がすっきりする:子ども部屋や寝室に大きなクローゼットを設ける必要がなくなるため、その分、部屋を広く使えたり、レイアウトの自由度が高まったりします。物が少なくなることで、掃除もしやすくなります。
- 家族間の情報共有がしやすい:子どもの衣類のサイズアウトや、誰がどんな服を持っているかを把握しやすくなります。衣替えも一か所で済むため、手間と時間を節約できます。
特に、共働き世帯や小さなお子さんがいるご家庭にとって、ファミリークローゼットは家事の時短に大きく貢献する魅力的な選択肢と言えるでしょう。
デメリットと注意点
一方で、ファミリークローゼットにはいくつかのデメリットや、計画時に注意すべき点も存在します。
採用を検討する際は、これらの点も十分に理解しておく必要があります。
まず、ある程度の広いスペースが必要になることです。
家族全員分の衣類を収納するためには、最低でも3畳以上の広さが推奨されます。
このスペースを確保するために、他の居住空間が犠牲にならないか、家全体のバランスを考える必要があります。
また、プライバシーの確保も課題です。
思春期の子どもがいる場合、家族共有のスペースで着替えることに抵抗を感じるかもしれません。
家族の誰かが着替えている間は他の人が入れない、といった気遣いが必要になる場面も出てくるでしょう。
間取りを工夫して、家族の動線が交錯しないように配慮したり、クローゼット内に間仕切りやカーテンを設けたりする対策が考えられます。
計画する際のポイント
ファミリークローゼットを成功させるためには、配置と内部設計が鍵となります。
前述の通り、配置は「回遊動線」を意識することが重要です。
「玄関→ファミリークローゼット→洗面所」や「洗面所→ファミリークローゼット→物干し場」といった、生活や家事の流れに沿った場所に設けることで、そのメリットを最大限に引き出すことができます。
内部設計においては、家族それぞれのエリアを大まかに決めておくと良いでしょう。
ハンガーパイプを2段にする、可動棚を多く取り入れるなど、収納する衣類の種類や量に合わせて柔軟に変化させられる設計が理想的です。
また、湿気対策として、窓や換気扇を設置することも忘れてはならないポイントです。
多くの衣類を収納する空間だからこそ、風通しを良くしてカビや臭いを防ぐ工夫が求められます。
場所別で見る注文住宅の収納アイデアと実例
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 食材管理が楽になるパントリーの活用法
- 玄関をすっきり見せる土間収納の魅力
- 参考になるおしゃれな注文住宅の収納実例
- 収納スペースで変わる費用の目安
- 理想の注文住宅の収納を実現する総まとめ
食材管理が楽になるパントリーの活用法

キッチン周りの収納力を格段にアップさせ、日々の調理や食材管理を楽にしてくれるのが「パントリー」です。
パントリーとは、主に食品や飲料、日用品のストックなどを収納するためのスペースのことを指します。
ここでは、パントリーの種類や活用法、計画のポイントについて詳しく見ていきましょう。
パントリーの種類と特徴
パントリーには、大きく分けて2つのタイプがあります。
それぞれの特徴を理解し、キッチンの広さやライフスタイルに合ったタイプを選ぶことが大切です。
- ウォークインタイプ:人が中に入れる小部屋のようなパントリーです。1畳から3畳程度の広さが一般的で、大容量の収納が可能です。食品ストックだけでなく、普段あまり使わない調理家電や、ゴミ箱などを置くスペースとしても活用できます。壁一面に可動棚を設置すれば、収納量を最大限に確保できます。
- 壁面タイプ(キャビネットタイプ):キッチンの壁の一部を利用して作る、奥行きの浅い収納スペースです。ウォークインタイプほどの広さは必要なく、省スペースで設置できるのがメリットです。扉を開ければ収納物全体を見渡せるため、在庫管理がしやすいという特徴があります。
まとめ買いをすることが多いご家庭や、災害用の備蓄をしっかりしておきたい場合にはウォークインタイプが、限られたスペースを有効活用したい場合には壁面タイプが適していると言えるでしょう。
パントリー活用のポイント
パントリーを最大限に活用するためには、いくつかのポイントがあります。
まず、収納する物の定位置を決め、ラベリングをすることです。
カゴやボックスを使って種類ごとに分類し、「乾物」「レトルト食品」「お菓子」のようにラベルを貼っておけば、家族の誰もが必要な物をすぐに見つけられます。
また、棚は「可動式」にするのがおすすめです。
収納する物の高さに合わせて棚板の高さを変えられるようにしておけば、スペースを無駄なく使うことができます。
特に、ペットボトルや調味料のボトルなど、高さのあるものを収納する際に重宝します。
さらに、ウォークインタイプの場合は、換気への配慮も重要です。
食品を扱うスペースなので、湿気や熱がこもらないように、窓や換気扇を設置して風通しを良くする工夫をしましょう。
計画時の注意点
パントリーを計画する際、最も重要なのは「キッチンからの動線」です。
調理中にサッと物を取り出せるように、キッチンからのアクセスが良い場所に配置しましょう。
玄関からの動線を考慮し、ウォークスルーにできると、買い物から帰ってきた際の収納作業が非常に楽になります。
また、奥行きにも注意が必要です。
奥行きが深すぎると、奥の物が取り出しにくくなり、「賞味期限切れ」の原因にもなりかねません。
一般的に、棚の奥行きは30cmから45cm程度が使いやすいとされています。
収納したい物を具体的にイメージしながら、最適なサイズを検討することが成功の鍵です。
玄関をすっきり見せる土間収納の魅力
家の顔である玄関は、常にすっきりと片付いた状態を保ちたいものです。
しかし、靴だけでなく、傘、ベビーカー、子どもの外遊び用おもちゃ、アウトドア用品など、玄関周りは何かと物で溢れがちです。
そんな悩みを解決してくれるのが「土間収納」です。
土間収納とは?
土間収納とは、玄関から土足のまま入れる収納スペースのことを指します。
シューズクロークやシューズインクローゼット(SIC)と呼ばれることもあります。
靴を履いたまま出入りできるため、屋外で使う物を気兼ねなく収納できるのが最大の魅力です。
土や泥で汚れた物でも、室内に持ち込むことなく片付けられます。
土間収納に何をしまう?
土間収納の活用方法は、家族のライフスタイルによって様々です。
一般的には、以下のような物が収納されます。
- 靴・傘:家族全員分の靴や長靴、ブーツ、傘などをまとめて収納できます。
- アウトドア・スポーツ用品:キャンプ用品、バーベキューセット、ゴルフバッグ、スノーボードなど、かさばる趣味の道具を収納するのに最適です。
- 子ども用品:ベビーカー、三輪車、外遊び用のおもちゃ、ボールなどをしまっておけば、公園に出かける準備もスムーズです。
- DIY用品・工具:ガーデニング用品や、日曜大工の工具などを収納する場所としても活躍します。
- その他:防災グッズ、灯油のポリタンク、ゴミの一時置き場など、様々な用途で活用できます。
このように、土間収納は単なる下駄箱ではなく、多目的に使える便利な外部収納としての役割を果たしてくれるのです。
計画する際のポイント
土間収納を計画する際には、いくつかのポイントを押さえておくと、より使い勝手が良くなります。
まず、広さは最低でも1.5畳から2畳程度確保できると、ベビーカーなども楽に出し入れできます。
収納したい物の量を事前にリストアップし、必要な広さを検討しましょう。
内部には、高さや位置を変えられる「可動棚」を設置するのが基本です。
ブーツや長靴など高さのある物もすっきりと収納できます。
また、濡れたコートやレインコートをかけておけるように、ハンガーパイプを一本設置しておくと非常に便利です。
臭いや湿気対策も重要です。
窓や換気扇を設けて、空気の通り道を確保しましょう。
壁材に、消臭・調湿効果のあるエコカラットなどの機能性タイルや、珪藻土、漆喰といった自然素材を採用するのもおすすめです。
さらに、コンセントを設置しておくと、電動自転車のバッテリーを充電したり、DIY工具を使ったりする際に役立ちます。
玄関からの動線も考慮し、来客用と家族用で動線を分ける「ウォークスルー」タイプにすると、玄関が常に片付いた状態をキープしやすくなります。
参考になるおしゃれな注文住宅の収納実例

注文住宅の収納は、機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりたいものです。
ここでは、おしゃれで参考になる収納の実例を場所別にご紹介します。
「見せる収納」と「隠す収納」のバランスや、素材選びの工夫など、自分らしい空間づくりのヒントを見つけてください。
リビング収納の実例
家族が集まるリビングは、すっきりとしつつも温かみのある空間にしたいものです。
リビング収納の定番は、壁面いっぱいに設ける「造作テレビボード」です。
テレビ周りにAV機器やDVD、本などをまとめて収納することで、空間に統一感が生まれます。
扉付きの「隠す収納」と、お気に入りの雑貨を飾るオープンスペースの「見せる収納」を組み合わせることで、デザイン性と機能性を両立できます。
間接照明を仕込めば、夜にはムーディーな雰囲気を演出することも可能です。
また、リビングの一角に小上がりの畳スペースを設け、その床下を引き出し収納にするアイデアも人気です。
子どものおもちゃや、ブランケットなど、リビングで使う物をサッとしまえて便利です。
キッチン収納の実例
キッチンは、デザイン性と清掃性の両立が求められる場所です。
最近のトレンドは、吊戸棚をなくし、オープンな「見せる収納」を取り入れたキッチンです。
壁面に木製の棚板を取り付け、お気に入りの食器や調理器具、スパイスボトルなどをカフェのようにディスプレイします。
開放感が生まれ、キッチン全体が明るい印象になります。
一方で、生活感の出やすい調理家電やゴミ箱などは、背面にある大容量のカップボードやパントリーに「隠す収納」としてまとめます。
カップボードの扉を、壁の色と合わせることで、収納の存在感を消し、空間をより広く見せる効果も期待できます。
取っ手のないプッシュオープン式の扉を選ぶと、さらにミニマルで洗練された印象になります。
その他の場所の収納実例
- 洗面所:鏡の裏を収納にした「ミラーキャビネット」は定番ですが、さらに壁面にニッチを設け、タオルやディフューザーを置くとホテルライクな空間になります。洗面台の下は、ファイルボックスや引き出しを使って、洗剤や掃除用具を整理整頓します。
- 寝室:ウォークインクローゼットの壁紙を一面だけアクセントクロスにしたり、おしゃれな照明を取り付けたりすることで、ただの収納スペースではなく、お気に入りの空間に変わります。ベッドのヘッドボードを造作し、本やスマートフォンを置けるニッチを作るのも便利なアイデアです。
- 廊下・ホール:壁の厚みを利用した「壁面本棚」は、廊下をギャラリーのような空間に変えてくれます。家族の写真やアートを飾るスペースとしても活用できます。奥行きはあまり取れないため、文庫本や漫画などの収納に適しています。
これらの実例のように、収納はアイデア次第で、家を彩るデザイン要素にもなり得ます。
自分たちの好みやライフスタイルに合わせて、機能的でおしゃれな収納を計画してみましょう。
収納スペースで変わる費用の目安
注文住宅で収納を計画する際、避けて通れないのが費用の問題です。
どれくらいの収納を設けると、どの程度の費用がかかるのか、目安を知っておくことは、現実的な予算計画を立てる上で非常に重要です。
ここでは、収納スペースの種類別に、費用の目安や考え方について解説します。
収納の費用を決める要素
収納スペースの費用は、主に以下の要素によって変動します。
- 面積:当然ながら、収納スペースが広くなるほど、床・壁・天井の材料費や工事費が増加します。
- 内部の仕様:棚板の数や材質、ハンガーパイプの有無、引き出しの設置など、内部の造作が複雑になるほどコストは上がります。
- 扉の有無と種類:オープンな棚に比べて、扉を付けると費用が加算されます。扉の種類も、開き戸、引き戸、折れ戸などによって価格は異なります。
- 追加設備:照明やコンセント、換気扇などを設置する場合、別途電気工事費が必要になります。
単純な「押し入れ」のような空間を作るのと、内部を細かく造作したウォークインクローゼットを作るのでは、同じ面積でも費用は大きく変わってくるのです。
種類別・費用の目安
一般的な注文住宅において、各収納スペースを追加する場合の費用目安は以下の通りです。
ただし、これらはあくまで一般的な相場であり、ハウスメーカーや工務店、仕様によって大きく異なるため、参考程度にお考えください。
| 収納の種類 | 一般的な広さ | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウォークインクローゼット | 2畳~4畳 | 20万円~50万円 | 棚板やハンガーパイプの数、扉の有無で変動。 |
| パントリー | 1畳~2畳 | 15万円~40万円 | ウォークインか壁面か、可動棚の数で変動。 |
| 土間収納(シューズクローク) | 1.5畳~3畳 | 15万円~40万円 | 床の仕上げ材、棚やパイプの設置で変動。 |
| 階段下収納 | 0.5畳~1畳 | 5万円~15万円 | 扉の設置や内部造作の有無で変動。 |
| 造作家具(壁面収納など) | - | 30万円~100万円以上 | 規模、デザイン、材質によって大きく変動する。 |
※上記は、建物の坪単価とは別に、追加で発生する費用の目安です。
コストを抑える工夫
予算には限りがありますから、必要な収納を確保しつつ、コストを抑える工夫も知っておきたいところです。
一つの方法は、収納内部の造作をシンプルにすることです。
例えば、クローゼット内部はハンガーパイプと枕棚だけを造作してもらい、引き出し収納などは市販の収納ケースやチェストを後から自分で置く、という形にすれば、造作費用を抑えられます。
また、扉を付けずにオープンな収納にするのもコストダウンにつながります。
ロールスクリーンやカーテンで目隠しをすれば、プライバシーを確保しつつ、扉よりも安価に仕上げることが可能です。
どこにお金をかけ、どこでコストを調整するか、優先順位を決めて計画することが重要です。
設計士とよく相談し、予算内で最大限の満足を得られるような収納計画を立てましょう。
理想の注文住宅の収納を実現する総まとめ

これまで、注文住宅の収納計画における後悔のパターンから、成功のコツ、具体的なアイデア、そして費用に至るまで、多岐にわたる情報をお伝えしてきました。
理想の注文住宅の収納とは、単に物が多くしまえるということではありません。
それは、家族一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、日々の暮らしをスムーズにし、心を豊かにしてくれる空間であるべきです。
計画の段階では、まず自分たちの「現在」を直視し、持ち物の量を正確に把握することから始まります。
そして、新しい家での暮らしを具体的にシミュレーションし、生活動線や家事動線上に、最適な収納を配置していく作業が続きます。
このとき、5年後、10年後といった「未来」の変化を見据える視点も忘れてはなりません。
パントリーやファミリークローゼット、土間収納といった人気の設備も、自分たちの暮らしに本当に必要か、メリット・デメリットを理解した上で採用を検討することが大切です。
そして、収納は機能性だけでなく、おしゃれや自分らしさを表現する場にもなり得ます。
「見せる収納」と「隠す収納」を巧みに使い分け、造作家具や素材選びにこだわることで、収納空間は家全体を彩る魅力的な要素へと昇華するでしょう。
もちろん、そこには予算という現実的な制約も伴います。
どこに投資し、どこをシンプルにするか、優先順位を明確にすることが、後悔のない選択につながります。
注文住宅の収納計画は、まさに「暮らしをデザインする」作業そのものです。
この記事で得た知識を元に、設計士や家族とじっくりと話し合い、あなただけの理想的な注文住宅の収納を実現してください。
fa-file-powerpoint-o
この記事のまとめ
- 注文住宅の収納計画は暮らしの快適さを左右する重要要素
- 失敗パターンは収納量の過不足や動線に合わない配置
- 成功のコツは持ち物リスト作成と生活シミュレーション
- 将来のライフスタイル変化を予測した計画が不可欠
- 収納率の数字より自分に合った量と場所が重要
- 間取りは「使う場所の近くにしまう」が基本原則
- ウォークスルー収納は家事動線を短縮し効率を上げる
- 階段下や壁面などデッドスペースの活用は有効な手段
- 造作家具は空間の統一感と機能性を高める
- 収納内部のコンセントや照明計画は使い勝手を向上させる
- ファミリークローゼットは洗濯動線を簡潔にするがプライバシーに配慮が必要
- パントリーは食材ストックに便利でキッチン動線が鍵
- 土間収納はアウトドア用品や汚れた物を気兼ねなくしまえる
- 「見せる収納」と「隠す収納」の使い分けでおしゃれな空間を演出
- 収納費用は面積や内部仕様で変動し予算計画が大切