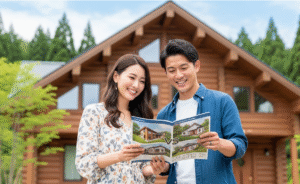注文住宅を建てる上で、理想の土…

自然に囲まれた木の家、ログハウスでの暮らしに憧れを抱いている方は多いのではないでしょうか。
しかし、実際にハウスメーカーでログハウスを建てようとすると、どのメーカーを選べば良いのか、価格や費用はどれくらいかかるのか、そして後悔しないためには何に気をつければ良いのか、様々な疑問が浮かんでくることでしょう。
この記事では、ハウスメーカーのログハウス建築を検討しているあなたのために、メーカーの比較やランキングから、人気のBESSやTALOといった具体的なブランドの特徴、おしゃれな平屋プランのポイント、気になる坪単価やキットの価格まで、あらゆる情報を網羅的に解説します。
さらに、ログハウス特有のデメリットやメンテナンスの問題、理想の暮らしを実現するためのプランニング、建築後のインテリアや内装の考え方など、住宅としてのログハウスを深く理解し、失敗しないための知識を提供します。
国産材か北欧材か、木の家の専門家であるハウスメーカーの施工事例を参考にしながら、あなたの理想の暮らしを形にするための第一歩を、この記事と共に踏み出してみましょう。
fa-hand-pointer-o
この記事で分かる事、ポイント
- 人気のログハウスメーカーのランキングと各社の特徴
- 大手メーカーBESSや本格派TALOの具体的な魅力
- おしゃれな平屋ログハウスを建てる際の価格やポイント
- ログハウスの坪単価やキットを利用した際の費用感
- 事前に知っておくべきログハウスのデメリットと対策
- メンテナンス費用や固定資産税などの維持費に関する知識
- 後悔しないためのメーカー選びとプランニングのコツ
理想の暮らしを叶えるハウスメーカー ログハウスの選び方
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 人気のログハウスメーカーをランキングで比較
- 大手BESSで建てるログハウスの特徴とは
- フィンランド直輸入の本格派TALOの魅力
- おしゃれな平屋ログハウスを建てる際のポイント
- 気になる費用は?ログハウスの坪単価と価格
- 通販のキットでセルフビルドはできるのか
人気のログハウスメーカーをランキングで比較

ハウスメーカーでログハウスを建てる決心をしたものの、数あるメーカーの中からどこを選べば良いのかは、最初の大きな課題です。
ここでは、日本国内で人気のある主要なログハウスメーカーを比較し、それぞれの特徴を分かりやすくランキング形式でご紹介します。
メーカー選びは、ログハウスでの暮らしの質を左右する最も重要な要素の一つと言えるでしょう。
デザインの方向性、使用する木材の種類、価格帯、そして提供されるサポート体制など、各社に特色があります。
あなたの理想とするライフスタイルや予算に最も合ったメーカーを見つけるための参考にしてください。
主要ログハウスメーカー比較表
以下に代表的なメーカーの特徴をまとめました。
もちろん、この他にも地域に根ざした優れたビルダーが数多く存在しますので、情報収集の第一歩としてご活用いただければ幸いです。
| メーカー名 | 特徴 | 価格帯の目安 | 得意なスタイル |
|---|---|---|---|
| BESS | 「住む」より「楽しむ」がコンセプト。多様なモデルと暮らしの提案が魅力。 | 中〜高価格帯 | カントリー、モダン、個性的 |
| TALO | フィンランド産木材にこだわる本格派。自由設計のプランが豊富。 | 中〜高価格帯 | 北欧、モダン、都市型 |
| ホンカ | 世界60カ国以上で実績を持つフィンランドの老舗。高品質なマシンカットが特徴。 | 高価格帯 | 北欧、トラディショナル |
| ビックボックス | ミニログから本格的な住宅まで幅広いラインナップ。キット販売も積極的。 | 低〜中価格帯 | ミニログ、カントリー、シンプル |
| フェニックスホーム | 長野県を拠点とし、国産材を活かした家づくりに定評。 | 中価格帯 | 和風、モダン、カントリー |
このランキングはあくまで一例であり、各メーカーの強みは様々です。
例えば、都市部での建築実績が豊富なメーカーや、寒冷地仕様に特化したメーカーも存在します。
大切なのは、資料請求やモデルハウス訪問を通じて、各社のログハウスにかける想いや技術力を直接感じることです。
ウェブサイトの施工事例を眺めるだけでも、各社のデザインの方向性や得意とするプランが見えてきます。
自然素材である木を扱うからこそ、そのメーカーがどのような哲学を持っているのかを比較検討することが、満足のいく家づくりに繋がるのです。
大手BESSで建てるログハウスの特徴とは
ログハウスメーカーの中でも、ひときわ高い知名度と人気を誇るのがBESSです。
全国に「LOGWAY」と呼ばれる単独展示場を展開し、ログハウスの魅力を多くの人に伝えています。
BESSの最大の特徴は、単に家という「箱」を売るのではなく、そこに住むことで得られる「暮らし」や「楽しみ」を提案している点にあります。
BESSが提案する多様な暮らしの形
BESSのラインナップは非常に多彩で、従来のログハウスのイメージに留まらない個性的なモデルが揃っています。
- あきつログハウス:日本の伝統的な美意識とログハウスを融合させたモデル。深い軒や縁側が特徴です。
- G-LOG:三角屋根と広いベランダ「NIDO(ニド)」が印象的なモデル。自然との一体感を楽しめます。
- WONDER DEVICE:ガルバリウム鋼板の外壁と木の内装を組み合わせた、遊び心あふれるスタイリッシュなモデルです。
- カントリーログハウス:太いログ材を使った、ログハウスらしい重厚感と温かみを感じられる王道モデルと言えるでしょう。
これらのモデルは、それぞれが明確なコンセプトを持っており、ユーザーは自身のライフスタイルや価値観に合ったものを選ぶことができます。
薪ストーブのある暮らし、DIYを楽しむ暮らし、庭で仲間と集う暮らしなど、BESSの家は常にアクティビティと共にあると言っても過言ではありません。
BESSを選ぶということは、単に建物を手に入れるだけでなく、その家を中心としたコミュニティやライフスタイルに参加することを意味します。
全国のLOGWAYでは定期的にイベントが開催され、オーナー同士の交流も活発です。
家を建てて終わりではなく、その後の暮らしまで楽しみたいと考える人にとって、BESSは非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
ただし、その独特の世界観が自分の価値観と合うかどうかを、展示場でじっくりと体感し、見極めることが重要です。
無垢材をふんだんに使った空間の心地よさや、少し不便だけれども愛着の湧く暮らしのスタイルを、心から楽しめるかどうかがポイントになります。
フィンランド直輸入の本格派TALOの魅力

本格的な北欧デザインのログハウスを求めるなら、フィンランド直輸入のTALOは外せない選択肢の一つです。
TALOはフィンランド語で「家」を意味し、その名の通り、ログハウスの本場である北欧の暮らしと品質を日本の住環境に届けています。
最大の特徴は、厳しい寒さの中でゆっくりと育った高密度な「フィンランドパイン(欧州赤松)」を構造材に使用している点です。
この木材は、ねじれや収縮が少なく、ログハウスの品質を長期にわたって安定させる上で非常に重要な役割を果たします。
自由設計で叶える理想の住まい
TALOのもう一つの大きな魅力は、その高い設計自由度にあります。
決まった規格プランから選ぶだけでなく、顧客一人ひとりの要望に合わせて間取りやデザインを構築していく「フリープラン」を得意としています。
都市部の狭小地や変形地といった厳しい敷地条件でも、経験豊富な設計士が最適なプランを提案してくれるでしょう。
「こんな暮らしがしたい」という漠然としたイメージを、具体的な形にしてくれる提案力がTALOの強みです。
例えば、大きな吹き抜けのある開放的なリビング、趣味に没頭できるアトリエスペース、景色を切り取る大きな窓など、夢に描いた空間を現実のものにすることが可能です。
また、モダン、トラディショナル、和風といった様々なデザインテイストに対応できる柔軟性も持ち合わせています。
ウェブサイトには数多くの施工事例が掲載されており、それらを眺めているだけでも、家づくりの夢が膨らみます。
品質の高いフィンランド産木材を使い、自分たちのライフスタイルに完全にマッチした、世界に一つだけのログハウスを建てたいと考える人にとって、TALOは最高のパートナーとなり得るハウスメーカーです。
もちろん、その品質と自由度の高さは価格にも反映されますが、長く愛せる本物の木の家を手に入れるための投資と考えることができるのではないでしょうか。
おしゃれな平屋ログハウスを建てる際のポイント
近年、住宅市場全体で人気が高まっている平屋ですが、そのトレンドはログハウスの世界でも同様です。
ワンフロアで生活が完結する平屋は、階段の上り下りがなく、家族間のコミュニケーションが取りやすいなど、多くのメリットがあります。
特に、木の温もりを存分に感じられるログハウスと平屋の組み合わせは、非常に相性が良いと言えるでしょう。
おしゃれで快適な平屋のログハウスを実現するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
開放感とプライバシーの両立
平屋のログハウスを設計する上で最も重要なのは、間取りの工夫です。
ワンフロアであることのメリットを最大限に活かすためには、LDKを中心に据えた開放的な空間設計が基本となります。
勾配天井にして吹き抜けのような縦への広がりを持たせたり、リビングと繋がるウッドデッキを設けたりすることで、実際の床面積以上の広がりを感じさせることが可能です。
一方で、家族それぞれのプライバシーを確保することも忘れてはなりません。
- LDKなどのパブリックスペースと、寝室や書斎などのプライベートスペースを明確に分離する。
- 廊下や収納スペースを効果的に配置し、部屋同士が直接隣接しないように工夫する。
- 中庭(パティオ)を設けることで、採光と通風を確保しつつ、外からの視線を遮る。
これらの工夫により、平屋ならではの繋がりと、個々の時間を尊重する暮らしが両立できます。
また、デザイン面では、屋根の形状が外観の印象を大きく左右します。
シンプルな片流れ屋根はモダンでスタイリッシュな印象を与え、どっしりとした切妻屋根は伝統的なログハウスの趣を感じさせます。
外壁の塗装色や窓の配置によっても、家の表情は大きく変わるでしょう。
平屋のログハウスは、シニア世代の終の棲家としてだけでなく、子育て世代にとっても魅力的な選択肢です。
将来的な家族構成の変化にも対応しやすい柔軟性を持ち合わせているため、長く快適に暮らせる住まいとなる可能性を秘めています。
気になる費用は?ログハウスの坪単価と価格

ログハウスを建てる上で、誰もが最も気になるのが費用に関することでしょう。
一体どれくらいの予算を見込んでおけば良いのか、その目安となるのが「坪単価」です。
しかし、ハウスメーカーのログハウスの価格は、様々な要因によって大きく変動するため、一概に「坪単価いくら」と言い切るのは難しいのが現実です。
ここでは、ログハウスの価格を構成する要素と、大まかな目安について解説します。
ログハウスの価格を左右する要因
ログハウスの建築費用は、主に以下の3つの要素で構成されます。
- 本体工事費:ログハウスの構造体や内外装、建具など、建物そのものにかかる費用です。坪単価で語られるのは、主にこの部分になります。
- 付帯工事費:地盤改良、給排水工事、外構工事、電気・ガス工事など、建物を建てるために必要な周辺の工事費用です。
- 諸経費:設計料、建築確認申請費用、登記費用、火災保険料、住宅ローン関連費用など、工事費以外にかかる様々な費用を指します。
一般的に、総費用のうち本体工事費が70~80%、付帯工事費と諸経費がそれぞれ10~15%程度を占めると言われています。
そして、本体価格の目安となる坪単価ですが、これはメーカーや仕様によって大きく異なります。
比較的リーズナブルなメーカーであれば坪50万円台から、高品質な輸入材や国産材を使用するメーカー、あるいは自由設計のプランでは坪80万~100万円以上になることも珍しくありません。
重要なのは、提示された坪単価に何が含まれているかを正確に確認することです。
メーカーによっては、最低限の仕様での坪単価を提示している場合もあります。
照明器具やカーテン、薪ストーブなどが別途オプション扱いになっていないか、詳細な見積もりを取り、総額で比較検討することが不可欠です。
例えば、30坪のログハウスを建てる場合、坪単価70万円であれば本体工事費は2,100万円となりますが、これに加えて付帯工事費や諸経費で数百万円が別途必要になると考えておくべきでしょう。
安易な坪単価の数字だけに惑わされず、資金計画は余裕を持って立てることが、後悔しない家づくりの第一歩です。
通販のキットでセルフビルドはできるのか
ログハウスの建築方法を調べていると、「キット」という言葉を目にすることがあります。
これは、ログハウスの主要な部材(ログ材、窓、ドア、屋根材など)がセットになったもので、通販などで購入することが可能です。
キットを利用することで、建築費用を大幅に抑えられる可能性があるため、特にセルフビルド(自分で家を建てること)に興味がある方にとっては魅力的に映るかもしれません。
しかし、キットを使ったセルフビルドには、相応の覚悟と知識、そして時間が必要です。
セルフビルドの現実と注意点
ログハウスのキット価格は、小さな小屋のようなモデルであれば数十万円から、住宅として使える規模のものでも数百万円台から見つけることができます。
ハウスメーカーに依頼する場合と比較すると、その価格は非常に安価です。
しかし、これはあくまで部材の価格であり、建築を完成させるまでには様々なハードルが存在します。
まず、建築基準法に適合した家を建てるためには、専門的な知識が不可欠です。
基礎工事や建築確認申請、複雑な構造計算など、素人が独力で乗り越えるのは非常に困難な作業と言えるでしょう。
また、ログ材を一段ずつ組み上げていく作業は、想像以上の重労働であり、多くの人手と時間を要します。
週末だけの作業では、何年もかかってしまう可能性も否定できません。
そのため、現実的な選択肢としては、「ハーフビルド」という方法が挙げられます。
これは、基礎工事やログ組み、屋根工事といった専門技術が必要な部分をプロの業者に依頼し、内装の塗装やウッドデッキの製作など、比較的難易度の低い部分を自分たちで行うというものです。
この方法であれば、コストを抑えつつ、家づくりに参加する楽しみも味わうことができます。
完全にセルフビルドを目指すのであれば、まずは小さな物置やサウナ小屋などのミニログから挑戦し、経験を積んでから住宅に挑むのが賢明です。
通販のキットは魅力的な選択肢ですが、その手軽さの裏にある困難さを十分に理解した上で、自分たちのスキルやかけられる時間と相談して、慎重に検討する必要があると言えるでしょう。
後悔しないためのハウスメーカー ログハウス建築の知識
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 事前に知っておきたいログハウスのデメリット
- メンテナンス費用や固定資産税について
- ライフスタイルに合わせた間取りの考え方
- 実際に建てた人の後悔から学ぶ失敗しないコツ
- まとめ:最高のハウスメーカー ログハウスで理想の家を
事前に知っておきたいログハウスのデメリット

木の温もりや自然との一体感など、多くの魅力を持つログハウスですが、一般的な住宅とは異なる特性を持っているのも事実です。
憧れだけで建築を進めてしまうと、住み始めてから「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。
ここでは、契約前に必ず知っておくべきログハウス特有のデメリットと、その対策について解説します。
デメリットを正しく理解し、受け入れることが、満足のいくログハウスライフを送るための鍵となります。
セトリング(木の収縮)への対応
ログハウスの最も特徴的な現象が「セトリング」です。
これは、積み上げられたログ材が、その自重と乾燥によって数年かけて少しずつ沈み込む現象を指します。
セトリング自体は、ログ材がしっかりと組み合わさっていく証拠でもありますが、これを見越した設計と施工がなされていないと、様々な不具合が生じます。
- 窓やドアの開閉不良:セトリングによって建具に圧力がかかり、開け閉めが困難になることがあります。
- 間仕切り壁の不具合:ログ壁と、セトリングしない間仕切り壁との間に隙間が生じることがあります。
- 雨漏りの原因:ログ材の間に隙間ができ、雨水が侵入するリスクが高まります。
信頼できるハウスメーカーであれば、セトリング対策は当然のこととして行われます。
窓やドアの上部にはあらかじめ隙間(セトリングスペース)を設け、間仕切り壁にはスライド機構を取り付けるなどの工夫が施されます。
また、壁を貫通するボルト(通しボルト)を定期的に締め直すことで、ログ壁全体の沈み込みを均一に促すメンテナンスも必要です。
メンテナンスの手間とコスト
ログハウスは「生きている家」とも言われ、その美しい外観と性能を維持するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
特に重要なのが、外壁の再塗装です。
紫外線や雨風から木材を保護している塗料は、時間と共に劣化します。
立地条件にもよりますが、一般的には5年から10年に一度の再塗装が推奨されています。
この費用は数十万円から百万円以上かかることもあり、あらかじめ資金計画に組み込んでおく必要があります。
また、ログハウスは虫がつきやすいというイメージを持つ方もいるかもしれませんが、現代のログハウスでは、建築時に防腐・防蟻処理が施された木材を使用するのが一般的です。
これらのデメリットを負担と感じるか、それとも家に手をかける楽しみと捉えるかで、ログハウスへの満足度は大きく変わってくるでしょう。
メンテナンス費用や固定資産税について
ログハウスでの暮らしを長期的に考える上で、避けて通れないのが維持費の問題です。
前述のメンテナンス費用に加えて、毎年納める必要がある固定資産税についても、事前に理解を深めておくことが重要です。
これらのランニングコストを把握しておくことで、無理のない資金計画を立てることができます。
定期メンテナンスの具体的な内容と費用
ログハウスのメンテナンスは、日常的にできる小さなことから、専門業者に依頼する大規模なものまで様々です。
- セルフメンテナンス:窓周りのコーキングのチェックや補修、ウッドデッキの塗装など、自分で行える範囲のメンテナンスです。
- 通しボルトの増し締め:セトリングを促すために、入居後数年間は定期的にボルトを締め直す作業が必要です。メーカーの指示に従って行います。
- 外壁の再塗装:最も費用がかかるメンテナンス項目です。足場を組む必要があるため、高額になりがちです。費用を抑えるためにDIYで行う人もいますが、高所作業には危険が伴います。
外壁塗装の費用は、家の大きさや塗料の種類によって変動しますが、100万円前後を見ておくと安心です。
この費用を10年ごとにかかると仮定すれば、年間10万円程度をメンテナンス費用として積み立てておく計算になります。
ログハウスの固定資産税は高いのか?
「ログハウスは木造だから固定資産税が安い」あるいは「嗜好性が高いから高い」といった噂を聞くことがありますが、実際のところはどうなのでしょうか。
固定資産税は、自治体が算出する「固定資産税評価額」に標準税率(1.4%)を乗じて計算されます。
この評価額は、建物の構造、使用されている資材、設備のグレードなどによって決まります。
ログハウスの場合、「木造」であるため、鉄骨造やRC造の建物に比べると評価額は低くなる傾向にあります。
しかし、一般的な木造軸組工法(在来工法)の住宅と比較した場合、ログ材をふんだんに使用していることや、太い梁や柱などが「贅沢な仕様」と見なされ、評価額が若干高くなるケースもあります。
結論として、ログハウスの固定資産税が、他の木造住宅に比べて極端に高いということはありません。
ただし、延床面積が同じでも、使用している木材の量や質、設備のグレードによって税額は変わってきます。
正確な金額を知りたい場合は、建築を依頼するハウスメーカーに、同様の物件での過去の事例を尋ねてみると良いでしょう。
ライフスタイルに合わせた間取りの考え方

せっかく自由設計が可能なハウスメーカーでログハウスを建てるのですから、間取りはとことんこだわりたいポイントです。
見た目のおしゃれさや流行だけでなく、自分たちの現在の、そして将来のライフスタイルに寄り添った、本当に暮らしやすい間取りを考えることが重要になります。
ここでは、後悔しないための間取り計画のヒントをいくつかご紹介します。
「動線」を意識したゾーニング
快適な間取りの基本は、スムーズな生活動線にあります。
特に、毎日何度も行き来する家事動線は、できるだけ短くシンプルにまとめるのがセオリーです。
例えば、キッチン、パントリー(食品庫)、洗面脱衣室、物干しスペースを回遊できるように配置すると、料理をしながら洗濯をするといった一連の作業が効率的に行えます。
また、来客時にプライベートな空間を見られずに済むよう、玄関からLDKへの動線と、パブリックスペースを通らずに寝室や水回りへ行ける動線を分けておく「来客動線」の考慮も大切です。
家族のライフスタイルを具体的にシミュレーションすることが、最適な動線を見つける近道です。
朝起きてから家を出るまで、帰宅してから寝るまで、休日の過ごし方など、家族一人ひとりの動きを紙に書き出してみると、必要な部屋の配置や繋がりが見えてきます。
将来の変化を見越した可変性
家は、何十年という長い時間を過ごす場所です。
建築時の家族構成が、ずっと続くとは限りません。
子供の成長や独立、あるいは親との同居など、将来のライフステージの変化に対応できるような、可変性のある間取りを考えておくことも賢明です。
例えば、子供部屋は、最初は大きな一つの部屋として使い、成長に合わせて間仕切り壁や家具で二部屋に分けられるようにしておく、といった工夫が考えられます。
ログハウスは構造壁が多いため、後から間取りを大きく変更するのは難しい場合があります。
そのため、設計段階で、将来的なリフォームや使い方の変更の可能性について、ハウスメーカーの設計士とよく相談しておくことが重要です。
収納スペースも、現在の荷物量だけでなく、将来増えることを見越して、十分な量を確保しておくと、後々の暮らしが快適になります。
実際に建てた人の後悔から学ぶ失敗しないコツ
これからログハウスを建てようとする人にとって、最も参考になるのが、実際に建てて住んでいる先輩たちの「生の声」です。
特に、成功体験だけでなく、「こうすればよかった」という後悔のポイントには、失敗を未然に防ぐための貴重なヒントが詰まっています。
ここでは、ログハウスのオーナーが感じがちな後悔のポイントと、それを避けるためのコツを学びましょう。
よくある後悔ポイントとその対策
多くのオーナーが挙げる後悔ポイントは、いくつかのパターンに分類できます。
- メンテナンスの大変さ:「思った以上に再塗装の費用と手間がかかる」「セトリングの調整が面倒」といった声です。対策としては、建築前にメンテナンス計画と費用を具体的にシミュレーションし、覚悟を決めておくことが挙げられます。
- 間取りの失敗:「収納が足りなかった」「吹き抜けが広すぎて冬寒い」「コンセントの位置と数が不便」など。これは、現在の暮らしだけでなく、将来のライフスタイルや家具の配置まで具体的にイメージして設計することで防げます。
- 立地の選択ミス:「自然豊かな場所を選んだが、スーパーや病院が遠くて不便」「虫が多い」といった問題。憧れだけでなく、日々の生活の利便性とのバランスを現実的に考えることが重要です。
- 夏の暑さ対策不足:ログハウスは断熱性が高いですが、一度温まると冷えにくい性質も持っています。特に、西日が当たる大きな窓は、夏の室温上昇の大きな原因になります。深い軒や遮熱性の高い窓ガラスを採用する、風通しを考慮した窓の配置にするなどの対策が有効です。
これらの後悔を防ぐために最も重要なのは、ハウスメーカーの担当者や設計士と、徹底的にコミュニケーションを取ることです。
自分たちの希望やライフスタイルを余すところなく伝え、同時にプロからの提案や懸念点にも真摯に耳を傾ける姿勢が求められます。
完成見学会やオーナー訪問の機会があれば、積極的に参加し、実際に住んでいる人のリアルな感想を聞くのも非常に有効です。
「格好良いから」という理由だけで薪ストーブを設置したものの、薪の確保や煙突掃除が大変で使わなくなってしまった、というのもよく聞く話です。
一つ一つの設備や仕様について、そのメリットだけでなく、運用していく上でのデメリットや手間まで理解し、納得した上で採用することが、後悔しない家づくりの最大のコツと言えるでしょう。
まとめ:最高のハウスメーカー ログハウスで理想の家を

ここまで、ハウスメーカーでログハウスを建てるための様々な情報をお伝えしてきました。
メーカーの選び方から、価格、間取り、そして後悔しないための注意点まで、多くの知識を得ていただけたのではないでしょうか。
ログハウスは、単なる住居ではなく、暮らしそのものを豊かにしてくれる特別な存在です。
木の香りに包まれ、季節の移ろいを肌で感じながら過ごす毎日は、何物にも代えがたい価値をもたらしてくれるでしょう。
しかし、その魅力を最大限に引き出すためには、信頼できるパートナー、すなわち最高のハウスメーカー ログハウスの専門家を見つけることが不可欠です。
BESSやTALOといった大手から、地域に根差した工務店まで、各社それぞれに魅力と特徴があります。
平屋や二階建て、キットの活用など、選択肢は多岐にわたりますが、最も重要なのは、あなたの家族がそこでどのような暮らしをしたいのか、そのビジョンを明確に持つことです。
この記事で得た知識を元に、ぜひ複数のメーカーから資料を取り寄せ、モデルハウスに足を運んでみてください。
そして、自分たちの夢を熱意を持って聞いてくれる、信頼できる担当者と出会うことができれば、理想のログハウスづくりは半分成功したと言っても過言ではありません。
デメリットやメンテナンスの手間も、愛着を持って家に手をかける楽しみと捉え、あなただけの素晴らしい木の家を、最高のハウスメーカーと共に実現してください。
fa-file-powerpoint-o
この記事のまとめ
- ハウスメーカーのログハウス選びは理想の暮らしの第一歩
- 人気メーカーはランキングや比較サイトで特徴を把握する
- BESSは暮らしの楽しみ方を提案するユニークな存在
- TALOはフィンランド直輸入の木材と自由設計が魅力
- おしゃれな平屋のログハウスは現代のニーズにマッチ
- 価格は坪単価だけでなく総額で比較検討することが重要
- ログハウスのキットでのセルフビルドは相応の覚悟が必要
- デメリットであるセトリングやメンテナンスを理解しておく
- 外壁塗装などのメンテナンス費用は計画的に準備する
- 固定資産税は他の木造住宅と大差ないが仕様による
- 間取りは生活動線と将来の可変性を考慮して計画する
- 実際に建てた人の後悔から失敗しないコツを学ぶ
- 夏の暑さや冬の寒さ対策は設計段階で盛り込む
- 信頼できるハウスメーカーとの出会いが成功の鍵
- 最高のハウスメーカーと唯一無二のログハウスを実現する