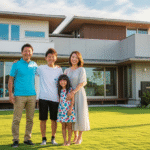アイフルホームで…

マイホームの完成、誠におめでとうございます。
新しい生活への期待に胸を膨らませる一方で、新築祝い 両家への対応について、どのように進めれば良いか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
特に、それぞれの実家からのお祝いとなると、金額の相場はいくらが適切なのか、品物と現金どちらが良いのか、またタイミングやマナーについても気になる点が多いものです。
さらに、兄弟からのお祝いや、お返しとしての内祝いをどうするか、感謝の気持ちを伝えるための食事会やお披露目会は開くべきか、お礼状の準備など、考えるべきことは山積みです。
中には、片方の親だけからお祝いをいただくケースもあり、その場合の対応に苦慮することもあるかもしれません。
このように、新築祝いにまつわる両家とのやり取りは、今後の良好な関係を築く上で非常に重要なイベントと言えるでしょう。
この記事では、そうした新築祝いに関するあらゆる疑問や不安を解消するために、必要な情報を網羅的に解説していきます。
fa-hand-pointer-o
この記事で分かる事、ポイント
- 新築祝いを両家の親から頂く場合の金額相場
- 兄弟から新築祝いをもらう際の目安
- お祝いを頂いた際の基本的なマナーとタイミング
- 感謝を伝える食事会やお披露目会の必要性
- 内祝い(お返し)の金額相場とおすすめの品物
- のしやお礼状に関する正しい知識と書き方
- 片方の親からだけお祝いを頂いた時の考え方と対応
新築祝いを両家から頂く時の疑問とマナー
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 親から頂くお祝いの金額相場はどのくらい?
- 兄弟からもらう場合の金額も知っておこう
- お祝い金か品物か、どちらが多い?
- 感謝を伝えるお披露目の食事会は開催すべきか
- 新築祝いを頂くタイミングと基本的なマナー
親から頂くお祝いの金額相場はどのくらい?

新築という人生の大きな節目において、両家の親からいただくお祝いは大変ありがたいものです。
しかし、その一方で「一体いくらぐらいいただくのが一般的なのだろう」と気になる方も少なくないでしょう。
結論から言うと、親からの新築祝いの金額に決まったルールはありませんが、一般的な相場としては50万円から100万円程度が一つの目安とされています。
中には100万円を超える高額なお祝いをいただくケースや、逆に「援助はできないけれど、気持ちだけ」と、もう少し控えめな金額になることもあります。
この金額の幅は、それぞれの家庭の経済状況や地域性、また親子間の関係性によって大きく変わるためです。
例えば、親がまだ現役で働いているか、年金生活に入っているかによっても、包める金額は大きく異なります。
また、これまでの兄弟姉妹への援助額とのバランスを考慮する親御さんもいらっしゃるでしょう。
重要なのは、金額の多寡に一喜一憂するのではなく、お祝いをしてくれるその気持ちに心から感謝することです。
もし、事前に金額について話す機会があれば、夫婦で希望を伝え、両家で金額の差が出ないように調整をお願いするのも一つの方法です。
ただし、お金の話はデリケートなため、伝え方には十分な配慮が必要となります。
以下に、一般的な相場をまとめますが、あくまで参考として捉え、各家庭の事情を鑑みることが大切です。
| 関係性 | 新築祝いの金額相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 自分の親 | 50万円~100万円 | 経済状況や地域差が大きい。これ以上、これ以下の場合も多数。 |
| 義理の親 | 50万円~100万円 | 両家で差が出ないように、事前に夫婦で話し合うことが望ましい。 |
| 夫婦合計 | 100万円~ | 家具や家電の購入費用として援助されるケースも多い。 |
最終的には、いただいたお祝いに対して誠心誠意の感謝を伝え、今後の生活を豊かにしていくことが何よりの恩返しになります。
金額はあくまで一つの形であり、その背景にある親の愛情や応援の気持ちをしっかりと受け止めるようにしましょう。
兄弟からもらう場合の金額も知っておこう
親からのお祝いと同様に、兄弟姉妹から新築祝いをいただくケースも多いです。
兄弟からの新築祝いの相場は、一般的に3万円から10万円程度とされています。
これも親からの場合と同じく、兄弟の年齢や経済状況、結婚しているかどうか、またこれまでの関係性によって金額は変動します。
例えば、まだ独身で若い兄弟であれば1万円から3万円程度でも十分な気持ちの表れですし、すでに家庭を持っている年長の兄や姉であれば5万円から10万円程度を包んでくれることもあります。
特に、自分が先に兄弟の結婚祝いや出産祝いなどを贈っている場合、その時の金額を参考にしてくれることが多いようです。
兄弟姉妹間では、お互いの状況がよく分かっているため、無理のない範囲でお祝いを贈り合うのが一般的です。
もし高額なお祝いをもらってしまった場合、かえって相手に気を遣わせてしまう可能性もあります。
そのため、もし兄弟から「お祝いは何がいい?」と聞かれた際には、現金であれば控えめな金額を伝えたり、「新しい時計が欲しいな」といったように具体的な品物をリクエストしたりするのも良いでしょう。
そうすることで、相手も気兼ねなくお祝いを贈ることができます。
- 20代の兄弟(独身):1万円~3万円
- 30代以降の兄弟(既婚):3万円~10万円
- 自分が先に贈ったお祝いの額が参考になることが多い
兄弟という近い関係だからこそ、形式ばったやり取りよりも、お互いを思いやる気持ちが大切になります。
いただいたお祝いに対しては、親しい中にも礼儀を忘れず、しっかりと感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。
電話やメッセージはもちろんのこと、新しい家に招待することが、何よりのプレゼントになるはずです。
お祝い金か品物か、どちらが多い?

新築祝いとしていただくものは、現金(お祝い金)と品物のどちらのケースもあり得ます。
どちらが多いかという点については、贈る側との関係性や考え方によって異なりますが、一般的には現金でいただくことが多い傾向にあります。
その理由として、現金であれば受け取った側が本当に必要なものを自分たちの好みやタイミングで購入できるというメリットがあるからです。
新築時には、家具や家電、カーテン、庭の整備など、何かと物入りになります。
そうした費用の一部として自由に使える現金は、非常に実用的で助かるというのが本音でしょう。
一方で、品物でお祝いをいただくことにも素敵な側面があります。
例えば、「この絵を飾ってほしい」「この時計をリビングに」といったように、贈る側の気持ちが形として残るのが品物の良い点です。
特に親や親しい兄弟からは、記念になるような家具や家電、アート作品などをいただくこともあります。
ただし、品物の場合は、家の雰囲気や自分たちの好みに合わないというリスクもゼロではありません。
そのため、贈る側が品物を選びたいと考えている場合は、「何か欲しいものはない?」と事前にリクエストを聞いてくれることが多いです。
もしリクエストを聞かれたら、遠慮せずに具体的な希望を伝えるのがお互いにとって良い結果につながります。
例えば、「新しいダイニングテーブルが欲しいのですが、一部を援助していただけると嬉しいです」といった形で伝えれば、相手も予算に合わせて協力しやすくなります。
最終的に、現金と品物のどちらをいただくにしても、その背景にある「おめでとう」という気持ちは同じです。
現金であればその使い道を報告したり、品物であれば実際に使っている様子を写真で送ったりするなど、感謝の気持ちを行動で示すことが大切です。
感謝を伝えるお披露目の食事会は開催すべきか
新築祝いをいただいたら、その感謝の気持ちを伝える場として、新しい家にお招きする「お披露目会」や「食事会」を検討する方が多いでしょう。
結論から言うと、可能であればぜひ開催することをおすすめします。
お披露目会は、いただいたお祝いへのお返し(内祝い)を兼ねることができ、何よりも「この家を建てました」と両家の親や兄弟に直接見てもらう絶好の機会となるからです。
自分たちがこだわって建てた家を案内し、新しい生活の様子を見てもらうことは、親御さんにとって大きな喜びであり、安心材料にもなります。
お披露目会を開催するタイミング
お披露目会を開催するタイミングは、引っ越しが落ち着いた1ヶ月後から2ヶ月後くらいが一般的です。
あまり早すぎると片付けが追い付かず、逆に遅すぎるとお祝いをいただいてから時間が空きすぎてしまうため、この期間が目安とされています。
両家の都合を合わせる必要があるため、早めに日程調整を始めると良いでしょう。
食事会の内容
食事は、仕出し弁当やデリバリー、ケータリングなどを利用すると、当日の負担を軽減できます。
もちろん、手料理でおもてなしするのも素晴らしいですが、無理のない範囲で計画することが大切です。
大切なのは、豪華な食事よりも、和やかな雰囲気で会話を楽しむことです。
開催できない場合の対応
遠方に住んでいる、仕事の都合がつかない、体調が優れないなど、様々な理由でお披露目会を開催できない場合もあるでしょう。
その場合は、無理に開催する必要はありません。
代わりに、内祝いの品物をきちんと贈り、心のこもったお礼状を添えることで、感謝の気持ちを伝えましょう。
お礼状には、家の様子がわかる写真を同封すると、相手も喜んでくれるはずです。
「落ち着いたら、ぜひ遊びに来てくださいね」と一言添えることも忘れないようにしましょう。
新築祝いを頂くタイミングと基本的なマナー

新築祝いをいただくタイミングは、一般的に新居の完成後、引っ越しの前後が多いです。
具体的には、完成から入居までの期間や、入居後1ヶ月以内が目安となります。
親や兄弟など、ごく親しい間柄であれば、もっと早い段階で「お祝いとして」と現金を渡されることもあるかもしれません。
どのタイミングでいただいても、受け取る側のマナーとして最も重要なのは、お祝いをいただいたら、できるだけ早く、まずはお礼の連絡を入れることです。
理想は、いただいたその日のうちか、遅くとも翌日中には電話で直接感謝の気持ちを伝えましょう。
電話が難しい場合でも、まずは取り急ぎメッセージなどで連絡を入れ、後日改めて電話をするのが丁寧な対応です。
- お祝いを受け取る
- 当日か翌日中に、まずは電話で直接お礼を伝える
- 後日、改めてお礼状(手紙やはがき)を送る
- お披露目会に招待するか、内祝いの品物を贈る
お礼の電話では、ただ「ありがとう」と伝えるだけでなく、「おかげさまで、素敵な家具が買えそうです」「大切に使わせていただきます」など、具体的な喜びの言葉を添えると、相手にも気持ちがより伝わります。
品物をいただいた場合は、その品物に対する感想を述べると良いでしょう。
そして、口頭でのお礼とは別に、後日改めてお礼状を送るのが正式なマナーです。
特に目上の方や高額なお祝いをいただいた場合には、手紙やはがきで感謝の気持ちを形にすることが大切です。
お礼状は、お祝いをいただいてから1週間から2週間以内には送るように心がけましょう。
こうした一連の丁寧な対応が、今後の良好な関係を築く上で非常に重要になります。
親しい間柄であっても、礼儀を尽くすことを忘れないようにしましょう。
新築祝いを両家へお返しする際のポイント
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 内祝いとしてのお返しは基本的に必要?
- お返しの金額相場とおすすめの品物を紹介
- ご祝儀袋の「のし」に関する基本知識
- 感謝が伝わるお礼状の書き方と文例
- 片方の親からだけもらった場合の対応方法
- まとめ:新築祝いは両家の絆を深める好機
内祝いとしてのお返しは基本的に必要?

新築祝いをいただいたら、「お返しは必要なのだろうか?」と悩むかもしれません。
結論として、新築祝いに対するお返し、すなわち「新築内祝い」は、基本的に必要とされています。
内祝いとは、元々「身内のお祝い事のお裾分け」という意味合いがあり、いただいたお祝いに対する返礼品として贈るのが現在の一般的な習慣です。
特に、親や兄弟といった身内であっても、高額なお祝いや品物をいただいた場合には、感謝の気持ちを形にして示すことがマナーとされています。
ただし、これにはいくつかの例外、あるいは考慮すべき点が存在します。
お披露目会がお返し代わりになるケース
前述の通り、新居のお披露目会に招待し、食事やお酒でおもてなしをすることが、内祝いの代わりと見なされることがよくあります。
この場合、必ずしも別途品物を贈る必要はありません。
ただし、いただいたお祝いが非常に高額であった場合など、おもてなしだけでは不十分と感じる際には、お帰りの際に手土産としてちょっとした品物をお渡しすると、より丁寧な印象になります。
親から「お返しは不要」と言われた場合
親御さんによっては、「子どもの新しい生活のために」という気持ちから、「お返しは気にしなくていいよ」と言ってくれることも少なくありません。
その言葉に甘えることも一つの選択ですが、言葉通りに何もしないのではなく、何らかの形で感謝の気持ちを表すのが望ましい対応です。
例えば、高価な品物でなくても、旅行先のお土産や、ちょっとしたお菓子、夫婦で選んだプレゼントなどを「ありがとう」の言葉とともに贈ると喜ばれるでしょう。
「不要」と言われても、何かしらのアクションを起こすことで、こちらの感謝の気持ちが伝わり、相手も嬉しい気持ちになるものです。
基本的には「お返しは必要」と考え、状況に応じて柔軟に対応するのが良いでしょう。
お返しの金額相場とおすすめの品物を紹介
新築内祝いを贈る際、最も気になるのが金額の相場と品物選びです。
これらを適切に選ぶことで、感謝の気持ちをスマートに伝えることができます。
内祝いの金額相場
内祝いの金額相場は、いただいたお祝いの額の「3分の1」から「半額(半返し)」が一般的です。
例えば、10万円のお祝いをいただいた場合、内祝いの予算は3万円から5万円程度が目安となります。
特に、親や親戚から高額なお祝い(50万円や100万円など)をいただいた場合は、半返しにこだわらず、3分の1程度の金額で心のこもった品物を選ぶのが通例です。
高額すぎるお返しは、かえって相手に「お祝いを突き返された」というような印象を与えかねないため、配慮が必要です。
| いただいたお祝いの額 | 内祝いの目安額(3分の1~半額) |
|---|---|
| 3万円 | 1万円~1万5千円 |
| 5万円 | 1万5千円~2万5千円 |
| 10万円 | 3万円~5万円 |
| 30万円 | 10万円程度 |
| 50万円以上 | いただいた額の3分の1を目安に、無理のない範囲で |
おすすめの内祝いの品物
内祝いの品物は、相手の好みやライフスタイルを考慮して選ぶことが大切です。
自分ではあまり買わないような、少し上質なものが喜ばれる傾向にあります。
何を贈れば良いか迷った場合は、相手が自由に選べるカタログギフトも非常に人気があります。
- カタログギフト: 相手が好きなものを選べるため、失敗が少ない定番の選択肢です。
- タオルギフト: 上質な素材のタオルは、いくつあっても困らない実用的な贈り物として人気です。
- グルメ・スイーツ: 有名店の焼き菓子や、高級なお肉、お米など、消え物でありながら特別感を演出できます。
- 食器類: ペアのグラスやカップなど。ただし、相手の好みが分かれるため、シンプルなデザインを選ぶのが無難です。
- 商品券・ギフトカード: 実用的ですが、金額が直接わかってしまうため、目上の方には避けた方が良い場合もあります。
品物選びに迷ったら、贈る相手である両親や兄弟に、それとなく欲しいものを聞いてみるのも良い方法です。
大切なのは、予算内で相手が喜んでくれるものを一生懸命選ぶ姿勢です。
ご祝儀袋の「のし」に関する基本知識

新築祝いを現金でいただく際には、ご祝儀袋、すなわち「のし袋」に入っていることがほとんどです。
そして、こちらが内祝いを贈る際にも、のしを掛けるのがマナーです。
のしには様々な種類があり、用途によって使い分ける必要がありますので、基本的な知識を身につけておきましょう。
水引の種類
新築祝いやその内祝いのように、何度あっても喜ばしいお祝い事には、「蝶結び(花結び)」の水引を使用します。
蝶結びは、何度も結び直せることから、「繰り返されると良いお祝い事」の際に用いられます。
一方で、結婚祝いのように一度きりが望ましいお祝い事には、「結び切り」や「あわじ結び」といった、一度結ぶと解けない水引が使われます。
この違いは必ず覚えておきましょう。
表書き(おもてがき)
のしの上段に書く言葉を「表書き」と言います。
お祝いをいただく側(ご祝儀袋)の表書き:
- 「御新築御祝」
- 「祝御新築」
- 「御祝」
お返しを贈る側(内祝いの品)の表書き:
- 「新築内祝」
- 「内祝」
内祝いの表書きは「新築内祝」とするのが最も丁寧ですが、「内祝」だけでも問題ありません。
名前の書き方
のしの下段には、贈り主の名前を書きます。
お祝いをいただく場合は、そこに両親や兄弟の名前が書かれています。
内祝いを贈る場合は、世帯主である夫の名前を中央に書き、その左に妻の名前を書くのが一般的です。
名字は中央に一つだけ書きます。
これらの知識は、新築祝いに限らず、今後の冠婚葬祭の様々な場面で役立ちます。
マナーとしてしっかりと押さえておくことで、相手に失礼のない、心のこもったやり取りができるようになります。
感謝が伝わるお礼状の書き方と文例
電話でのお礼に加えて、手書きのお礼状を送ることで、より一層深い感謝の気持ちを伝えることができます。
特に高額なお祝いをいただいた場合や、普段なかなか会えない親戚などには、ぜひお礼状を送りましょう。
ここでは、お礼状の基本的な構成と文例をご紹介します。
お礼状の基本的な構成
お礼状は、以下の構成で書くと、まとまりやすく、気持ちが伝わりやすくなります。
- 頭語と時候の挨拶: 「拝啓」で始め、季節に合った挨拶の言葉を続けます。
- お祝いへのお礼: いただいたお祝いの品や金額に触れ、感謝の言葉を述べます。
- 新生活の報告: 新しい家での暮らしの様子や、今後の抱負などを伝えます。いただいた品物を使っている様子などを具体的に書くと喜ばれます。
- 相手への気遣い: 相手の健康や近況を気遣う言葉を入れます。
- 結びの挨拶と結語: 「今後とも変わらぬお付き合いを」といった言葉で締め、「敬具」で結びます。
- 日付と署名: 日付と、夫婦連名での署名を記載します。
お礼状の文例
【親へ送る場合の文例】
拝啓
風薫るさわやかな季節となりましたが、お父さん、お母さんにおかれましては、お変わりなくお過ごしのことと存じます。
さて、この度は私達の新築に際し、心のこもったお祝いをいただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで、夢だったマイホームでの新生活を順調にスタートさせることができております。
いただいたお祝い金で、家族が集うリビングに素敵なソファを購入させていただきました。
新しい家は日当たりも良く、毎日快適に過ごしております。
ささやかではございますが、今度ぜひ一度、新しい我が家へ遊びに来てください。お会いできる日を楽しみにしております。
季節の変わり目ですので、くれぐれもご自愛ください。
敬具
令和〇年〇月〇日
〇〇 太郎
花子
このように、定型的な文章だけでなく、自分たちの言葉で具体的なエピソードを盛り込むことで、温かみのあるお礼状になります。
片方の親からだけもらった場合の対応方法

新築祝い 両家とのやり取りの中で、最もデリケートで悩ましいのが「片方の親からだけお祝いをいただいた」あるいは「両家で金額に大きな差がある」というケースです。
このような状況に直面すると、どう対応すれば良いか、夫婦の間で気まずい雰囲気になってしまうこともあるかもしれません。
まず最も大切な心構えは、両家を比較しないことです。
それぞれの家庭には、それぞれの経済状況や価値観、祝い事に対する考え方があります。
例えば、一方の親は「子どもの門出だから盛大に祝いたい」と考えるかもしれませんし、もう一方の親は「自分たちの老後の資金も考えなければならない」「援助よりも、静かに見守ることが愛情だ」と考えている可能性もあります。
そこに優劣はなく、どちらも子どもを思う気持ちの表れ方の一つに過ぎません。
お祝いをくれなかった、あるいは金額が少なかったからといって、愛情が薄いと判断するのは早計です。
具体的な対応方法
- いただいた側には、誠心誠意の感謝を伝える: まずは、お祝いをいただいた事実に対して、夫婦そろって心から感謝の気持ちを伝えましょう。いただいたお祝いを素直に喜び、大切に使う姿勢を見せることが何よりです。
- いただいていない側の親の気持ちを尊重する: お祝いがなかったとしても、決して責めたり、催促したりするような言動は慎むべきです。何か事情があるのかもしれないと相手の立場を尊重し、これまで通りに接することが重要です。新居が完成した報告はきちんと行い、「いつでも遊びに来てくださいね」と歓迎する姿勢を見せましょう。
- 夫婦間で情報を共有し、思いやりを持つ: この問題は夫婦間のコミュニケーションが鍵を握ります。自分の親がお祝いをくれなかった、あるいは少なかったことで、パートナーが肩身の狭い思いをしているかもしれません。お互いの親を尊重し、思いやりのある言葉をかけ合うことが大切です。
新築祝いは、あくまで「お祝いの気持ち」です。
金額や有無という形にこだわりすぎず、その背景にある両家の思いを汲み取り、夫婦で協力して乗り越えていくことで、家族の絆はより一層深まるはずです。
まとめ:新築祝いは両家の絆を深める好機
ここまで、新築祝いを両家からいただく際の様々な疑問やマナーについて詳しく解説してきました。
金額の相場やタイミング、お返しの仕方など、考えるべきことは多く、時に悩んでしまうこともあるかもしれません。
しかし、本来、新築祝いは新しい門出を祝う喜ばしいイベントです。
一連のやり取りは、これまで育ててくれた両家の親へ感謝を伝え、新しい家族の形を報告する絶好の機会と捉えることができます。
マナーやしきたりは、相手への敬意や感謝をスムーズに伝えるための知恵でもあります。
基本をしっかりと押さえつつも、最も大切なのは形式にこだわりすぎることなく、夫婦、そして両家とのコミュニケーションを密にすることです。
お祝いの金額に差があったり、予期せぬ事態が起こったりした時こそ、夫婦でよく話し合い、お互いの家族を思いやる姿勢が試されます。
この新築祝いというイベントを通じて、両家との関係がより良好になり、家族の絆がさらに深まることを願っています。
この記事で得た知識を参考に、自信を持って、そして何よりも感謝の気持ちを忘れずに、素晴らしい新生活のスタートを切ってください。
fa-file-powerpoint-o
この記事のまとめ
- 新築祝いを両家の親から頂く相場は50万から100万円が目安
- 兄弟からの新築祝いは3万から10万円が一般的
- 金額は家庭の事情や地域性により大きく異なるため比較しないことが重要
- お祝いは現金だけでなく家具や家電などの品物で頂くケースもある
- お祝いを頂いたらすぐに電話でお礼を伝え後日お礼状を送るのがマナー
- 新居へ招待するお披露目会はいただいたお祝いへのお返しを兼ねられる
- お披露目会が難しい場合は内祝いの品物を贈る
- 内祝いの金額相場はいただいた額の3分の1から半額が目安
- 高額な場合は3分の1程度とし高価すぎるお返しは避ける
- 内祝いの品はカタログギフトや上質なタオルなどが人気
- のし袋の水引は何度あっても良いお祝い用の「蝶結び」を選ぶ
- 内祝いの表書きは「新築内祝」または「内祝」とする
- 片方の親からだけお祝いを頂いても両家を比較せず感謝の気持ちを大切にする
- 夫婦でよく話し合いお互いの親を尊重する姿勢が家族円満の秘訣
- 新築祝いの両家とのやり取りは感謝を伝え家族の絆を深める良い機会となる