マイホームの購入や売却は、人生…

暮らしの変化に合わせて、住まいのスペースを広げたいと考えることは自然な流れです。
特に、高い品質と信頼性で知られる積水ハウスにお住まいの方にとって、増築は魅力的な選択肢の一つではないでしょうか。
しかし、その一方で「積水ハウスの増築費用は一体いくらかかるのだろう」という疑問や不安がつきまといます。
増築の計画を進める上では、坪単価の相場はもちろん、6畳や10畳といった具体的な広さでどの程度の費用感になるのかを把握することが重要です。
また、積水ハウス特有の軽量鉄骨という構造が、増築にどのような影響を与えるのか、場合によっては増築ができないケースもあるのか、といった専門的な知識も必要となります。
単純なリフォームとの比較検討や、平屋住宅の増築における特有の注意点も気になるところでしょう。
さらに、賢く費用を抑えるためには、利用可能な補助金制度の情報を集め、信頼できる業者から正確な見積もりを取得するプロセスが欠かせません。
この記事では、積水ハウスの増築費用に関するあらゆる疑問に答えるべく、費用の相場から見積もりの取り方、計画を進める上での具体的な注意点まで、網羅的に解説していきます。
fa-hand-pointer-o
この記事で分かる事、ポイント
- 積水ハウスの増築費用の坪単価と具体的な相場
- 増築とリフォームの費用や内容の比較
- 軽量鉄骨造で増築する場合の特性と制約
- 平屋や6畳・10畳スペースを増築する際の注意点
- 法的な理由で増築ができないケース
- 費用を抑えるために活用できる補助金制度
- 正確な見積もりを取るための業者選びのポイント
積水ハウス 増築 費用の相場と坪単価の内訳
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 増築とリフォームの比較でわかること
- 6畳や10畳スペースの増築にかかる坪単価
- 平屋を増築する場合の注意点
- 軽量鉄骨造ならではの特性と制約
- 増築できないケースとその理由
積水ハウスで増築を検討する際、多くの方が最も気になるのが費用面でしょう。
一体どのくらいの予算を見込んでおけば良いのか、その相場観を掴むことは計画の第一歩です。
この章では、積水ハウスの増築費用に関する基本的な知識として、坪単価の相場や具体的な内訳、そして費用を左右するさまざまな要因について詳しく解説していきます。
リフォームとの違いから、積水ハウスならではの構造的な特徴、法的な制約に至るまで、事前に知っておくべき情報を整理しました。
増築とリフォームの比較でわかること

住まいの改修を考えるとき、「増築」と「リフォーム」という言葉を耳にしますが、この二つは目的も費用も大きく異なります。
これらの違いを正確に理解することは、ご自身の希望に合った最適な選択をする上で非常に重要です。
まず、リフォームは既存の建物の枠内で改修を行うことを指します。
例えば、キッチンの設備を新しくしたり、壁紙を張り替えたり、間取りを変更したりといった工事がこれに該当します。
リフォームの最大のメリットは、工事の規模が比較的小さく、費用も増築に比べると抑えやすい点にあります。
一方で、増築は建物の「床面積を増やす」工事を意味します。
敷地内に新たな構造物を作って既存の建物とつなげたり、2階建てにして部屋を増やしたりすることが増築です。
これにより、物理的に居住スペースを広げることができるため、家族が増えたり、新しい趣味の部屋が欲しくなったりした場合に有効な手段となります。
費用面で比較すると、一般的に増築の方が高額になります。
なぜなら、増築には既存の建物の解体作業に加え、基礎工事、構造体の組み立て、屋根や外壁の設置といった大規模な工事が必要になるからです。
また、建築基準法に関わる「確認申請」という手続きが必要になるケースがほとんどで、そのための書類作成や申請にも費用と時間がかかります。
積水ハウスの増築費用を考える際には、このリフォームとの根本的な違いを認識しておくことが、正確な予算計画の前提となります。
単に内装を綺麗にしたい、設備を新しくしたいという希望であればリフォームで十分かもしれませんが、部屋数そのものを増やしたい、家全体を広くしたいという根本的な要望がある場合は、増築を選択することになるでしょう。
増築とリフォームのメリット・デメリット
具体的な違いをさらに明確にするために、それぞれのメリットとデメリットを整理してみましょう。
- 増築のメリット: 物理的に居住空間が広がる、ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる。
- 増築のデメリット: 費用が高額になる、工期が長くなる、建築基準法などの法的な制約を受ける。
- リフォームのメリット: 費用を比較的安く抑えられる、工期が短い、デザインや機能を一新できる。
- リフォームのデメリット: 床面積は増えない、既存の構造の制約を受けるため、間取り変更に限界がある。
このように、どちらが良いかは一概には言えず、ご自身の目的や予算、そして現在の住まいの状況によって最適な選択は変わってきます。
積水ハウスの住まいの価値を将来にわたって維持し、快適な生活を送るためにも、まずは専門家と相談し、増築とリフォーム、双方の可能性を検討することをおすすめします。
6畳や10畳スペースの増築にかかる坪単価
増築費用を具体的にイメージするために、「坪単価」という指標がよく用いられます。
坪単価とは、1坪(約3.3平方メートル)あたりの建築費用のことを指し、増築のおおよその費用を計算する際の目安となります。
積水ハウスの増築における坪単価は、工事の内容や建物の構造、使用する建材のグレードによって大きく変動しますが、一般的には70万円から110万円程度が相場とされています。
では、具体的な広さとしてよく検討される「6畳」と「10畳」のスペースを増築する場合、費用はどのくらいになるのでしょうか。
6畳は約3坪、10畳は約5坪に相当します。
この面積を基に、先ほどの坪単価を当てはめて計算してみましょう。
| 増築面積 | 広さ(坪数) | 費用相場(坪単価70万円の場合) | 費用相場(坪単価110万円の場合) |
|---|---|---|---|
| 6畳 | 約3坪 | 約210万円 | 約330万円 |
| 10畳 | 約5坪 | 約350万円 | 約550万円 |
上記の表からわかるように、同じ面積でも坪単価によって総額には大きな差が生まれます。
例えば6畳の増築であっても、200万円台で収まるケースもあれば、300万円を超えるケースもあるということです。
この価格差を生む要因は多岐にわたります。
例えば、増築部分を子供部屋にするのか、水回り設備を含む書斎にするのかで、内装工事や設備工事の費用が全く異なります。
また、既存の建物との接続部分の処理が複雑であったり、特殊な基礎工事が必要になったりする場合も費用は上乗せされます。
さらに、これらの工事費に加えて、設計料や確認申請費用、既存部分の解体費用、諸経費などが別途必要になることも忘れてはなりません。
したがって、坪単価はあくまで概算を掴むための目安と捉え、最終的な費用は必ず正式な見積もりで確認することが不可欠です。
積水ハウスリフォームなどの専門業者に相談すれば、現在の住まいの状況や希望する増築内容に基づいた、より詳細な費用感を提示してくれるでしょう。
平屋を増築する場合の注意点

近年、その暮らしやすさから再び注目を集めている平屋ですが、平屋を増築する際には特有の注意点がいくつか存在します。
積水ハウスの平屋にお住まいの方が増築を検討する際には、これらのポイントを事前に押さえておくことが、スムーズな計画進行の鍵となります。
平屋の増築方法には、大きく分けて「横に広げる(水平増築)」と「上に伸ばす(垂直増築)」の2種類があります。
まず、水平増築は、敷地に余裕がある場合に可能な方法で、既存の建物に新しい部屋をつなげるようにして床面積を増やします。
この方法の注意点としては、建ぺい率や容積率といった建築基準法の制限をクリアする必要があることです。
また、増築部分と既存部分の接続方法によっては、建物の耐震性に影響が出る可能性もあるため、構造計算をしっかりと行う必要があります。
特に、積水ハウスのような鉄骨造の場合、ユニットの追加や接続には専門的な知識と技術が求められます。
一方で、垂直増築は、既存の平屋の上に2階部分を増築する方法です。
敷地面積に余裕がない場合に有効な手段ですが、こちらはさらに高度な検討が必要となります。
最大の注意点は、既存の基礎や構造体が、2階部分の荷重に耐えられる設計になっているかという点です。
新築時に2階建てを想定していない平屋の場合、基礎の補強や大規模な構造改修が必要となり、費用が大幅に増加する可能性があります。
積水ハウスの住宅は頑丈な構造が特徴ですが、それでも垂直増築が可能かどうかは、専門家による詳細な構造診断が不可欠です。
診断の結果、増築が難しいと判断されるケースも少なくありません。
さらに、平屋の増築では、家全体のデザインバランスも重要な要素となります。
安易に増築を行うと、後から付け足したような不自然な外観になってしまう恐れがあります。
積水ハウスの洗練されたデザイン性を損なわないためにも、既存の建物との調和を考えた設計プランを立てることが望まれます。
屋根の形状や外壁材の色、窓の配置など、細部にわたって統一感を出す工夫が必要です。
軽量鉄骨造ならではの特性と制約
積水ハウスの住宅の多くは、「軽量鉄骨造」という独自の構法で建てられています。
この構造は、工場で生産された高品質な部材を現場で組み立てるプレハブ工法の一種であり、安定した品質と高い耐震性を実現しています。
増築を検討する際には、この軽量鉄骨造ならではの特性と、それに伴う制約を理解しておくことが非常に重要です。
まず、軽量鉄骨造の大きな特性は、柱や梁といった構造体がユニット化されている点です。
これにより、木造住宅に比べて設計の自由度がやや制限される場合があります。
例えば、壁を取り払って大きな空間を作りたいと考えても、構造上撤去できない「耐力壁」が存在することがあります。
増築においても同様で、既存の建物のどこに、どのように新しいユニットを接続するかは、構造的な強度を維持するために慎重な計画が求められます。
このため、積水ハウスの増築は、その構造を熟知している積水ハウスリフォーム、あるいは同社の住宅の改修経験が豊富な専門業者に依頼するのが最も安全で確実と言えるでしょう。
知識のない業者が安易に手を加えると、建物の耐震性や耐久性を著しく損なう危険性があるからです。
また、制約という面では、外壁パネルの仕様もポイントになります。
積水ハウスの外壁には、デザイン性や耐久性に優れた独自の部材が使用されています。
増築する際には、既存の外壁と新しい外壁のデザインや色合いを合わせる必要がありますが、年数が経過していると、全く同じ製品が廃番になっている可能性があります。
その場合、似たデザインの製品を探したり、場合によっては家全体の外壁をリフォームしたりする必要が出てくるかもしれません。
これは費用にも影響してくるため、事前に確認が必要です。
しかし、これらの制約はデメリットばかりではありません。
工場生産による部材の品質管理が徹底されているため、増築部分も新築時と同等の高い精度と性能を確保できるという大きなメリットがあります。
構造計算に基づいた確実な施工が行われるため、増築後の住まいも安心して長く暮らすことができるでしょう。
増築できないケースとその理由

増築を希望しても、残念ながら物理的、あるいは法的な理由で実現できないケースが存在します。
積水ハウスの増築費用を検討する前に、そもそもご自身の住まいが増築可能なのかどうか、基本的な条件を確認しておくことが大切です。
増築ができない最も一般的な理由は、建築基準法による制限です。
具体的には、「建ぺい率」と「容積率」という二つの規制が大きく関わってきます。
- 建ぺい率: 敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合のことです。例えば、建ぺい率が50%と定められている地域では、100平方メートルの土地に50平方メートルまでしか建物を建てられません。すでに上限まで建っている場合、水平方向への増築は原則として不可能です。
- 容積率: 敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合のことです。この規制は、主に建物の高さを制限する役割があります。こちらも上限に達している場合、2階建てにするなどの垂直増築はできません。
これらの規制は、都市計画法に基づいて地域ごとに細かく定められており、役所の建築指導課などで確認することができます。
また、土地によっては、隣地との境界線から一定の距離を離さなければならない「壁面後退」や、建物の高さを制限する「高さ制限」などの規制がある場合もあります。
これらの法的な規制をクリアできなければ、増築の計画を進めることはできません。
次に、物理的な理由として、建物の構造上の問題が挙げられます。
前述の通り、特に平屋を2階建てにするような垂直増築の場合、既存の基礎や構造体が2階部分の重さに耐えられないと判断されれば、増築は困難です。
これは住人の安全を確保するために最も重要な点であり、専門家による厳密な構造診断によって判断されます。
さらに、敷地の状況も増築の可否を左右します。
例えば、増築工事を行うための重機やトラックが進入できるスペースが確保できない、隣家との距離が近すぎて足場を組むことができない、といったケースです。
このような状況では、技術的に増築が可能であっても、工事に着手すること自体が難しい場合があります。
これらの理由から、増築を考え始めたら、まずは積水ハウスリフォームなどの専門業者に相談し、現地調査を依頼することが不可欠です。
専門家の視点から、法的な規制や建物の状態、敷地の状況などを総合的に判断してもらい、増築が可能かどうかを見極めることが、計画の第一歩となります。
積水ハウス 増築 費用を抑えるためのポイント
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 補助金制度の活用方法と申請の流れ
- 複数の業者から見積もりを取る重要性
- 費用を抑えるための具体的な注意点
- 他社ではできないと言われた時の対処法
- 積水ハウス 増築 費用の総まとめと計画の進め方
積水ハウスの増築は、快適な住空間を手に入れるための有効な手段ですが、決して安い買い物ではありません。
だからこそ、計画段階から費用を賢く抑えるための工夫を凝らすことが重要になります。
この章では、積水ハウスの増築費用を少しでも抑えるための具体的なポイントを多角的に解説します。
公的な補助金制度の活用から、適切な業者選び、工事内容の工夫まで、知っているだけで数十万円単位の差が生まれる可能性のある情報をまとめました。
補助金制度の活用方法と申請の流れ

増築やリフォームを行う際には、国や地方自治体が設けている補助金制度を利用できる場合があります。
これらの制度をうまく活用することで、積水ハウスの増築費用を大幅に軽減できる可能性があるため、計画の初期段階から情報収集を始めることを強くおすすめします。
増築で利用できる可能性のある補助金は、主に省エネ性能の向上や耐震性の強化、子育て支援などを目的としたものです。
代表的な制度には以下のようなものがあります。
主な補助金制度の例
- 子育てエコホーム支援事業: 省エネ性能の高い新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して補助金を交付する国の事業です。増築部分に高断熱の窓を設置したり、高効率の給湯器を導入したりする場合に対象となる可能性があります。
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業: 既存住宅の性能を向上させ、長く安心して住めるようにするためのリフォームを支援する制度です。耐震改修や省エネ改修など、一定の基準を満たす大規模な改修工事が対象となります。
- 地方自治体独自の補助金: お住まいの市区町村が独自に設けているリフォーム補助金制度も数多く存在します。例えば、三世代同居のための改修支援や、地域の木材を使用した改修への補助など、内容はさまざまです。
これらの補助金制度を利用するためには、それぞれ定められた要件を満たす必要があります。
例えば、使用する建材の性能基準や、工事を行う業者が登録事業者であることなどが条件となる場合があります。
申請の流れは制度によって異なりますが、一般的には以下のようになります。
- 情報収集: 国の機関や自治体のウェブサイト、リフォーム業者の担当者から情報を集めます。
- 対象工事の計画: 補助金の要件を満たすように、増築の工事内容を計画します。
- 申請手続き: 工事着工前に申請が必要な場合が多いため、必要書類を揃えて期限内に提出します。
- 工事の実施と完了報告: 交付決定後、工事を行い、完了後には実績報告書などを提出します。
- 補助金の交付: 報告書が受理された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
補助金制度は予算の上限に達し次第、受付が終了してしまうことが多いため、早めの情報収集と行動が鍵となります。
手続きが複雑で分かりにくい場合も多いので、積水ハウスリフォームなどの専門業者に相談し、申請のサポートを依頼するのも一つの有効な方法です。
複数の業者から見積もりを取る重要性
積水ハウスの増築費用を適正な価格で実現するためには、複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」が極めて重要です。
積水ハウスの増築だからといって、必ずしも積水ハウスリフォーム一社に絞る必要はありません。
もちろん、自社の建物を知り尽くしているという安心感は大きなメリットですが、他の業者と比較することで、より客観的な視点から費用や提案内容を判断することができます。
相見積もりを行う目的は、単に一番安い業者を見つけることだけではありません。
それぞれの業者がどのような提案をしてくれるのか、その内容を比較検討することに本当の価値があります。
相見積もりのチェックポイント
見積書を確認する際には、以下の点に注目しましょう。
- 総額だけでなく内訳の細かさ: 「工事一式」といった大雑把な記載ではなく、どのような工事にいくらかかるのかが詳細に記載されているかを確認します。詳細な見積もりを提出してくれる業者は、それだけ誠実で信頼できる可能性が高いと言えます。
- 提案内容: こちらの要望を汲み取った上で、さらにプロとしての付加価値のある提案が含まれているかを見ます。デザイン性や将来のメンテナンス性まで考慮された提案は、良い業者の証です。
- 担当者の対応: 質問に対して丁寧に、そして専門的な知識を持って答えてくれるか、こちらの不安に寄り添ってくれるかなど、担当者との相性も重要な判断基準です。長い付き合いになる可能性もあるため、信頼関係を築ける相手を選びましょう。
一般的に、3社程度の業者から見積もりを取るのが良いとされています。
多すぎると比較検討が煩雑になり、逆に少なすぎると客観的な判断が難しくなります。
積水ハウスの増築経験が豊富なリフォーム会社や、地域で評判の良い工務店などを候補に含めると良いでしょう。
最近では、インターネットの一括見積もりサイトなども活用できますが、最終的には必ず担当者と直接会い、会社の信頼性や実績を確認してから契約することが大切です。
手間はかかりますが、このプロセスを丁寧に行うことが、後悔のない増築につながります。
費用を抑えるための具体的な注意点
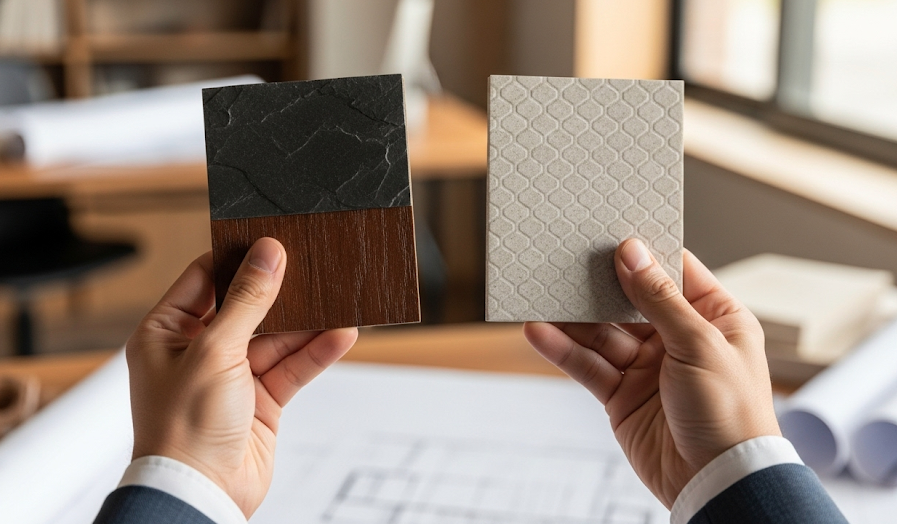
補助金の活用や相見積もりに加えて、増築の計画内容そのものを工夫することでも、費用を効果的に抑えることが可能です。
ここでは、積水ハウスの増築費用をコントロールするための具体的な注意点をいくつかご紹介します。
まず、最も費用に影響するのが、増築する面積と工事の規模です。
当然ながら、面積が広ければ広いほど、費用は高くなります。
計画段階で、「本当にその広さが必要か」をもう一度冷静に考えてみましょう。
例えば、収納スペースを増やす目的であれば、一部屋増やすのではなく、屋根裏や床下を活用した収納を設けることで、より低コストで目的を達成できるかもしれません。
次に、内装や設備のグレードを見直すことも有効な手段です。
壁紙や床材、ドアといった建材は、デザインや機能によって価格が大きく異なります。
全ての部分で最高級のグレードを選ぶのではなく、こだわりたい部分にはコストをかけ、あまり人目に付かない場所や使用頻度の低い場所は標準的なグレードのものを選ぶ、といったメリハリをつけることで、総額を調整することができます。
また、キッチンや浴室、トイレといった水回り設備の増設は、配管工事が伴うため費用が高額になりがちです。
可能であれば、水回りの増設は避け、既存の設備をリフォームするに留める、あるいは既存の配管から近い位置に設置するなどの工夫で、費用を抑えることができます。
さらに、工事のタイミングも考慮に入れると良いでしょう。
例えば、将来的に外壁や屋根のメンテナンスが必要になる時期に合わせて増築を行えば、足場を一度で済ませることができるため、別々に工事を行うよりもトータルコストを削減できます。
これらの工夫は、専門家であるリフォーム会社の担当者と相談しながら進めることが重要です。
こちらの予算を正直に伝えた上で、「この予算内で希望を叶えるにはどうすれば良いか」という視点で、プロならではのアイデアを提案してもらいましょう。
無理なコストカットは、建物の品質や安全性を損なうことにもなりかねませんので、専門家のアドバイスを参考に、賢い選択を心がけてください。
他社ではできないと言われた時の対処法
積水ハウスの増築を検討する中で、他のリフォーム会社に相談した際に「うちでは対応できない」「積水ハウスさんに頼んだ方が良い」と言われてしまうケースがあります。
これは、前述したように、積水ハウスの住宅が独自の軽量鉄骨構造(プレハブ工法)で建てられているためです。
この特殊な構造は、一般的な木造住宅の知識だけでは安全な増築を行うのが難しく、リスクを避けるために断る業者がいるのも無理からぬことです。
では、もし他社で断られてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。
まず、最も確実な選択肢は、やはり積水ハウスグループの「積水ハウスリフォーム」に相談することです。
彼らは自社の建物の構造を隅々まで熟知しており、新築時の図面などのデータも保管しているため、最も安全で最適な増築プランを提案してくれます。
費用面では他の業者より高くなる傾向があるかもしれませんが、建物の性能や保証を維持するという観点からは、これ以上ない安心感があると言えるでしょう。
しかし、どうしても他の選択肢を探したい、あるいは提案内容や費用を比較したいという場合は、諦める必要はありません。
次に取るべき対処法は、「ハウスメーカーのプレハブ住宅の増改築経験が豊富な業者」を探すことです。
全ての業者が対応できないわけではなく、中には積水ハウスをはじめとする大手ハウスメーカーの住宅の改修を専門的に手掛けている会社も存在します。
そうした業者は、軽量鉄骨造の特性を理解しており、適切な構造計算や施工方法のノウハウを持っています。
業者を探す際には、会社のウェブサイトで施工事例を確認し、積水ハウスの物件を手掛けた実績があるかどうかをチェックするのが有効です。
また、最初の問い合わせの段階で、「積水ハウスの軽量鉄骨造の増築ですが、対応可能ですか」とストレートに確認してみましょう。
その際の担当者の反応や知識レベルも、信頼できる業者かどうかを見極める一つの判断材料になります。
いずれにせよ、積水ハウスの増築は専門性が高い工事であることを念頭に置き、安易な業者選びは避けるべきです。
建物の大切な資産価値と安全を守るためにも、信頼できるパートナーを見つけることが何よりも重要です。
積水ハウス 増築 費用の総まとめと計画の進め方

これまで見てきたように、積水ハウスの増築費用は、増築の規模や内容、建物の状況、そして依頼する業者によって大きく変動します。
一概に「いくら」と言い切ることは難しいですが、計画を立てる上での基本的な考え方と進め方を最後にまとめておきましょう。
まず、費用の概算を掴むためには、坪単価70万円~110万円という相場を一つの目安とし、ご自身が希望する増築面積を掛け合わせてみてください。
例えば、子供部屋として6畳(約3坪)を増築する場合、おおよそ210万円~330万円ほどの本体工事費がかかると想定できます。
ただし、これに加えて設計料や申請費用、既存部分の改修費などの諸経費が必要になることを忘れないでください。
次に、計画の進め方ですが、何よりもまず専門家への相談から始めることが肝心です。
積水ハウスリフォーム、あるいはハウスメーカーの改修経験が豊富な業者に連絡を取り、現地調査を依頼しましょう。
その際には、なぜ増築したいのか、増築してどのような暮らしを実現したいのか、といった目的を明確に伝えます。
そして、予算の上限も正直に伝えることで、より現実的な提案を引き出すことができます。
複数の業者から提案と見積もりが出揃ったら、費用だけでなく、提案内容や担当者の対応などを総合的に比較検討し、最も信頼できる一社をパートナーとして選びます。
契約前には、工事の範囲や仕様、工期、そして支払い条件などを書面で詳細に確認し、少しでも疑問点があれば解消しておくことがトラブルを防ぐ上で重要です。
積水ハウスの増築は、単に家を広くするだけでなく、ご家族の未来の暮らしを豊かにするための投資です。
そのためには、しっかりとした情報収集と周到な計画が不可欠となります。
この記事で得た知識を元に、ぜひ後悔のない、満足のいく増築計画を進めてください。
fa-file-powerpoint-o
この記事のまとめ
- 積水ハウスの増築費用は坪単価70万円から110万円が目安
- 6畳の増築なら約210万円から330万円が相場
- 10畳の場合は約350万円から550万円が費用感となる
- 増築は床面積を増やす工事でリフォームとは根本的に異なる
- 積水ハウスは独自の軽量鉄骨造で専門知識が必要
- 構造上、増築には制約があり耐力壁の撤去は難しい
- 平屋の増築は水平増築と垂直増築の2種類がある
- 2階を増築する垂直増築は基礎や構造の強度が重要
- 建ぺい率や容積率など法規制で増築できない場合がある
- 費用を抑えるには国や自治体の補助金活用が有効
- 子育てエコホーム支援事業などが利用できる可能性がある
- 複数の業者から相見積もりを取り費用と提案を比較することが重要
- 内装や設備のグレードにメリハリをつけると費用を調整できる
- 他社で断られた場合は積水ハウスリフォームへの相談が確実
- 積水ハウスの増築は信頼できる業者選びが最も大切







