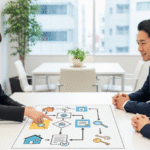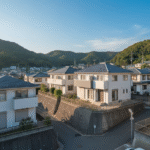マイホームの購入は、人生におけ…

住宅の購入やリフォームを検討する際、多くの方が耳にする住宅ローン控除とは、一体どのような制度なのでしょうか。
この制度は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した人の金利負担を軽減するための重要な税制優遇措置です。
しかし、その内容は複雑で、特に2025年にかけての制度変更もあり、いつまでに何をすれば良いのか、適用条件や計算方法、必要な書類を揃えて行う確定申告の流れなど、分からないことも多いかもしれません。
また、2年目以降の手続きや、中古住宅の購入、借り換えを検討している場合の扱いや、ご自身の年収でどれくらい控除されるのか、所得税だけでなく住民税にどう影響するのかといった点も気になるところでしょう。
この記事では、住宅ローン控除とは何かという基本的な仕組みから、最新の制度内容、具体的な手続きの方法まで、あらゆる疑問に答えていきます。
fa-hand-pointer-o
この記事で分かる事、ポイント
- 住宅ローン控除の基本的な仕組み
- 2025年度の制度改正の重要ポイント
- 控除を受けるための具体的な適用条件
- 控除額の計算方法と簡単なシミュレーション
- 初年度に行う確定申告の手順
- 2年目以降の年末調整での手続き
- 中古住宅やリフォーム、借り換え時の注意点
住宅ローン控除とは何かを分かりやすく解説
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- そもそも住宅ローン控除(減税)とはどんな制度?
- 2025年度の改正点とポイント
- 控除を受けるための適用条件
- 控除額はいくら?計算方法とシミュレーション
- 所得税で引ききれない場合は住民税からも控除
そもそも住宅ローン控除(減税)とはどんな制度?

住宅ローン控除、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
これは、個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得、または増改築等を行った場合に、年末のローン残高の一定割合に相当する金額が、納めるべき所得税や住民税から直接差し引かれる、つまり税金が安くなる制度です。
この制度の目的は、住宅取得者の金利負担を軽減し、良質な住宅ストックの形成を促進することにあります。
具体的には、毎年末の住宅ローン残高に0.7%を掛けた金額が、その年に納める所得税から控除されます。
例えば、年末のローン残高が3,000万円だった場合、その0.7%である21万円が、所得税から還付または減額される計算になります。
この控除は一度きりではなく、原則として入居した年から最長で13年間(中古住宅の場合は10年間)にわたって受けることができます。
したがって、総額で見ると数百万円単位での大きな節税効果が期待できる、非常にメリットの大きい制度と言えるでしょう。
ただし、控除される金額には上限があり、その上限額は取得する住宅の環境性能や入居する年によって変動します。
また、控除額はあくまで自身が納める税金の範囲内でのみ適用されるため、納めている所得税額が控除可能額よりも少ない場合は、全額を控除しきれないこともあります。
その場合でも、所得税から控除しきれなかった分は、翌年の住民税から一部控除される仕組みが用意されています。
この制度を最大限に活用するためには、その仕組みを正しく理解し、定められた期間内に適切な手続きを行うことが不可欠です。
特に初年度は、会社員の方であっても年末調整では手続きができず、ご自身で確定申告を行う必要があります。
マイホームの購入は人生で最も大きな買い物の一つですが、この住宅ローン控除という制度を賢く利用することで、その後の家計の負担を大きく軽減させることが可能になるのです。
2025年度の改正点とポイント
住宅ローン控除の制度は、経済状況や住宅政策に応じて、これまでも度々見直しが行われてきました。
特に2022年度の税制改正では、控除率が従来の1%から0.7%に引き下げられるなど大きな変更があり、その影響は2025年まで続きます。
これから住宅を購入する方、あるいはすでに検討を進めている方にとって、最新の制度内容を理解しておくことは極めて重要です。
最大のポイントは、住宅の環境性能によって借入限度額(控除の対象となる年末ローン残高の上限額)が細かく分けられている点です。
国が環境に配慮した質の高い住宅の普及を後押ししていることの表れと言えるでしょう。
具体的に、2024年および2025年に入居する場合の借入限度額と最大控除額は以下の表のようになります。
| 住宅の種類 | 2024年・2025年入居の場合の借入限度額 | 最大控除額(年間) |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 31.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 24.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 21万円 |
| その他の住宅(一般の新築住宅) | 0円 ※ | 0円 ※ |
※2023年末までに建築確認を受けた新築の「その他の住宅」は、2,000万円の借入限度額が適用され、最大14万円の控除が10年間受けられます。2024年以降に建築確認を受ける場合は、原則として対象外となります。
この表からわかるように、最も優遇されるのは「長期優良住宅」や「低炭素住宅」といった認定住宅で、借入限度額は4,500万円です。
一方で、最も注意すべきなのは「その他の住宅」の扱いです。
2024年以降に建築確認を受けた省エネ基準に適合しない新築住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外となってしまいました。
これは、今後の住宅は省エネ基準を満たしていることが当たり前になるという国の方針を明確に示しています。
これから新築物件を探す場合は、その物件がどの環境性能レベルに該当するのかを不動産会社やハウスメーカーに必ず確認することが重要です。
また、子育て世帯や若者夫婦世帯(19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が2024年に入居する場合、借入限度額が上乗せされる特例措置もあります。
例えば、長期優良住宅であれば限度額が5,000万円に、ZEH水準省エネ住宅であれば4,500万円に引き上げられます。
しかし、この特例も2025年には適用されず、上乗せなしの金額に戻る予定です。
このように、住宅ローン控控除の制度は入居する年や住宅の性能、世帯の状況によって内容が大きく異なります。
ご自身の状況と照らし合わせ、最新の情報を正確に把握することが、賢く制度を活用するための第一歩となります。
控除を受けるための適用条件

住宅ローン控除は非常に魅力的な制度ですが、誰もが無条件で利用できるわけではありません。
制度の適用を受けるためには、主に「人に関する要件」「住宅ローンに関する要件」「住宅に関する要件」の3つの側面から、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。
これらの条件を事前に確認しておかないと、いざ住宅を購入した後に控除が受けられないという事態になりかねません。
以下に、主な適用条件をまとめましたので、ご自身の状況が当てはまるかチェックしてみましょう。
人に関する主な要件
まず、控除を受ける人自身に関する条件です。
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 住宅を取得してから6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。
特に重要なのが合計所得金額です。
年収ではなく、給与所得控除やその他の所得控除を差し引いた後の金額が基準となります。
また、転勤などのやむを得ない事情がなく、すぐに居住しない場合は適用対象外となるため注意が必要です。
住宅ローンに関する主な要件
次に、利用する住宅ローンに関する条件です。
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること。
- 勤務先からの無利子または低金利(年0.2%未満)での借入金や、親族からの借入金ではないこと。
返済期間が10年未満のローンや、銀行などの金融機関以外からの個人的な借入れは、原則として控除の対象になりません。
住宅に関する主な要件
最後に、取得する住宅そのものに関する条件です。
- 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。(合計所得金額1,000万円以下の場合は40平方メートル以上に緩和)
- 床面積の2分の1以上が、自己の居住用であること。
- 中古住宅の場合は、一定の耐震基準を満たしていること。(例:1982年1月1日以降に建築された住宅など)
特に床面積の要件は、マンションなどで登記簿上の面積(内法面積)と、パンフレットなどに記載されている面積(壁心面積)が異なる場合があるため、必ず登記簿上の面積で確認する必要があります。
また、中古住宅の場合は建築年月が非常に重要になります。
古い物件であっても、「耐震基準適合証明書」や「既存住宅売買瑕疵保険への加入」など、耐震性を証明できれば控除の対象となる場合があります。
これらの条件は多岐にわたりますが、一つでも満たしていないと控除は受けられません。
住宅の購入を計画する段階で、これらの条件をクリアできるか、不動産会社や税理士などの専門家に相談しながら進めることが賢明です。
控除額はいくら?計算方法とシミュレーション
住宅ローン控除で実際にどれくらいの税金が戻ってくるのかは、最も気になるところだと思います。
控除額の計算は、一見複雑に思えるかもしれませんが、基本的な計算式は非常にシンプルです。
まず、基本となる計算式を理解しましょう。
年間の控除額 = 年末の住宅ローン残高 × 0.7%
この式で算出された金額が、その年に納めるべき所得税から直接差し引かれます。
ただし、この計算結果がそのまま控除額になるわけではなく、2つの上限が設けられています。
- 「借入限度額」に基づく上限
- 自身が納める「所得税・住民税」の額に基づく上限
一つ目の上限は、前述の通り、住宅の環境性能によって定められた「借入限度額」です。
例えば、省エネ基準適合住宅(2024年入居)の借入限度額は3,000万円です。
この場合、年末のローン残高が3,500万円あったとしても、計算の基礎となるのは3,000万円までとなります。
したがって、年間の最大控除額は「3,000万円 × 0.7% = 21万円」となります。
二つ目の上限は、自身がその年に納める所得税と、一部の住民税の合計額です。
住宅ローン控除は、あくまで納税額を限度とした減税制度です。
仮に計算上の控除額が30万円だったとしても、その年の所得税額が20万円であれば、所得税から控除されるのは20万円までです。
具体的なシミュレーション
ここで、具体的な例でシミュレーションしてみましょう。
- 年収:600万円(課税所得300万円、所得税額 約20万円、住民税額 約30万円)
- 住宅:ZEH水準省エネ住宅(借入限度額3,500万円)
- 借入額:4,000万円
- 初年度年末のローン残高:3,900万円
STEP1:控除可能額の計算
まず、年末ローン残高(3,900万円)は借入限度額(3,500万円)を超えているため、計算には3,500万円を用います。
控除可能額 = 3,500万円 × 0.7% = 24.5万円
STEP2:所得税からの控除
この年の所得税額は20万円です。
控除可能額24.5万円のうち、まずは所得税20万円の全額が控除されます。
これにより、所得税の納税額は0円になります。
STEP3:住民税からの控除
所得税から控除しきれなかった金額が残っています。
控除しきれない額 = 24.5万円 - 20万円 = 4.5万円
この4.5万円は、翌年の住民税から控除されます。
ただし、住民税からの控除にも上限(課税所得の5%、最大9.75万円)があります。
このケースでは、上限(300万円×5%=15万円)の範囲内なので、4.5万円全額が住民税から差し引かれます。
結果
最終的に、所得税20万円と住民税4.5万円の合計24.5万円が、この年の住宅ローン控除による減税額となります。
このように、ご自身の年収(納税額)と購入する住宅の性能、そしてローン残高の3つの要素によって、実際の控除額が決まります。
事前にシミュレーションしておくことで、将来の資金計画も立てやすくなるでしょう。
所得税で引ききれない場合は住民税からも控除

住宅ローン控除の大きな特徴の一つに、所得税だけでは控除しきれない分を、翌年度の住民税からも差し引くことができる仕組みがあります。
これは、特に所得税額がそれほど多くない方にとって、減税の恩恵を最大限に受けるための重要なポイントとなります。
前述のシミュレーションでも触れましたが、この仕組みについてもう少し詳しく解説します。
住宅ローン控除の控除額は、まずその年の所得税から差し引かれます。
しかし、年間の控除額(年末ローン残高 × 0.7%)が、納めるべき所得税額を上回るケースは少なくありません。
例えば、計算上の控除額が25万円であるのに対し、所得税額が18万円だったとします。
この場合、所得税は全額(18万円)が控除されて納税額はゼロになりますが、まだ7万円分(25万円 - 18万円)の控除枠が残ってしまいます。
もしこの7万円がそのまま切り捨てられてしまうと、制度の恩恵を十分に受けられません。
そこで、この所得税から控除しきれなかった金額を、翌年度に支払う住民税から差し引くことができるのです。
住民税からの控除には上限がある
ただし、住民税からいくらでも控除できるわけではなく、上限額が定められています。
その上限額は、以下のいずれか少ない方の金額となります。
- 所得税の課税総所得金額等の5%
- 97,500円
つまり、住民税からの控除額は最高でも97,500円までということです。
「課税総所得金額等」とは、年収から給与所得控除や基礎控除、社会保険料控除などを差し引いた後の金額で、源泉徴収票などで確認することができます。
例えば、課税総所得金額等が300万円の方であれば、その5%は15万円となりますが、上限は97,500円なので、住民税から控除できるのは最大97,500円までです。
もし所得税から控除しきれなかった額が10万円あったとしても、住民税から引かれるのは97,500円までとなり、差額の2,500円は控除されないことになります。
とはいえ、この住民税からの控除制度があるおかげで、より多くの人が住宅ローン控除のメリットを享受できるようになっています。
手続きは必要?
住民税からの控除を受けるために、何か特別な追加手続きが必要になるわけではありません。
初年度の確定申告や、2年目以降の年末調整を正しく行えば、税務署からお住まいの市区町村へ情報が連携されます。
その情報に基づいて、市区町村が自動的に翌年度の住民税額を計算してくれるため、ご自身で市区町村へ申告する必要はありません。
毎年5月~6月頃に勤務先経由または自宅に送られてくる「住民税決定通知書」を確認すれば、住宅ローン控除が適用されているかどうかが分かります。
住宅ローン控除の金額を考える際には、所得税だけでなく、この住民税からの控除分も視野に入れて全体像を把握することが大切です。
住宅ローン控除とは手続きが複雑?流れを解説
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 手続きの基本的な流れと必要書類
- 【初年度】確定申告での申請方法
- 2年目以降の手続きは年末調整で
- 中古住宅やリフォームの場合の注意点
- 借り換えでも住宅ローン控除は使える?
- 総括:住宅ローン控除とは賢く活用すべき制度
手続きの基本的な流れと必要書類

住宅ローン控除を受けるための手続きは、初年度と2年目以降で大きく異なります。
特に最初の年は、会社員や公務員の方であっても、ご自身で確定申告を行う必要があります。
この初年度の手続きさえ乗り越えれば、2年目以降は会社の年末調整で済むため、ぐっと楽になります。
まずは、手続きの全体像と、それに伴って必要となる書類を把握しておくことが重要です。
手続きの大きな流れ
- 初年度:入居した翌年の2月16日~3月15日に、税務署へ確定申告を行う。
- 2年目以降:勤務先の年末調整で手続きを行う。(自営業者などは引き続き確定申告が必要)
この流れが基本となります。
手続きを忘れてしまった場合でも、5年以内であれば遡って申告(還付申告)することが可能ですが、手間が増えるため、期間内に忘れずに行うようにしましょう。
必要となる主な書類
手続きには様々な書類が必要となります。
直前になって慌てないよう、早めに準備を始めることが大切です。
特に、法務局や金融機関から取り寄せる書類は時間がかかる場合があるので注意しましょう。
以下は、主に初年度の確定申告で必要となる書類の一覧です。
- 税務署で入手・作成する書類
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 勤務先から受け取る書類
- 源泉徴収票
- 金融機関から受け取る書類
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 法務局で入手する書類
- 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 不動産会社から受け取る書類
- 不動産売買契約書や工事請負契約書の写し
- その他、本人確認等で必要な書類
- マイナンバーカード(または通知カード+運転免許証など)
これらの書類のうち、「年末残高等証明書」は住宅ローンを組んでいる金融機関から毎年10月頃に送られてきます。
また、認定長期優良住宅など、住宅の性能に応じて控除の優遇を受ける場合は、その性能を証明するための「認定通知書の写し」なども別途必要になります。
書類に不備があると、税務署での手続きがスムーズに進まなかったり、再提出を求められたりすることがあります。
何が必要なのかをリストアップし、一つずつ着実に揃えていくことが、手続きを円滑に進めるコツです。
特に初めて確定申告を行う方は、国税庁のウェブサイト(e-Tax)や税務署の相談窓口などを活用するのも良いでしょう。
【初年度】確定申告での申請方法
住宅ローン控除を受けるための最初の関門が、初年度の確定申告です。
普段、確定申告に馴染みのない会社員の方にとっては、難しく感じるかもしれませんが、手順を追って進めれば決して難しいものではありません。
確定申告は、住宅に入居した翌年の2月16日から3月15日までの期間に行います。
確定申告の方法
申告には主に3つの方法があります。
- e-Tax(電子申告)を利用する: 自宅のパソコンやスマートフォンから、オンラインで申告手続きを完結させる方法です。マイナンバーカードと対応するICカードリーダライタ(またはスマホ)があれば、24時間いつでも申告が可能で、書類の提出も一部省略できるなどメリットが大きいです。
- 税務署の窓口へ直接提出する: 必要書類を持参して、管轄の税務署の窓口で直接提出する方法です。申告期間中は窓口が大変混み合うため、時間に余裕を持って行く必要があります。
- 郵送で提出する: 申告書を作成し、必要書類を添付して管轄の税務署へ郵送する方法です。この場合、通信日付印が提出日とみなされます。
近年は、国税庁もe-Taxの利用を推奨しており、ウェブサイト上の「確定申告書等作成コーナー」は、画面の案内に従って入力していくだけで自動的に税額が計算されるなど、非常に分かりやすくなっています。
初めての方でも比較的スムーズに申告書を作成できるため、特におすすめの方法です。
申告書作成の簡単な流れ(e-Taxの場合)
1. 事前準備
まずは前述の必要書類(源泉徴収票、年末残高等証明書、登記事項証明書など)をすべて手元に揃えます。
また、マイナンバーカードも用意しておきましょう。
2. 確定申告書等作成コーナーへアクセス
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「作成開始」ボタンをクリックします。
3. 収入・所得の入力
画面の案内に従い、源泉徴収票の内容(支払金額、所得控除の額、源泉徴収税額など)を正確に入力していきます。
4. 住宅ローン控除の入力
所得控除の入力画面で「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の項目を選択します。
すると、専用の入力画面が表示されるので、居住開始年月日や住宅の種別、年末のローン残高などを、「年末残高等証明書」や「計算明細書」を見ながら入力します。
ここで入力した内容に基づいて、控除額が自動で計算されます。
5. 申告書の送信
すべての入力が終わると、還付される税額が表示されます。
内容を確認し、還付金の振込先口座などを入力した後、マイナンバーカードを使って電子署名を行い、データを送信すれば手続きは完了です。
申告後、おおむね1ヶ月から1ヶ月半程度で、指定した口座に還付金が振り込まれます。
最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、一つ一つの項目を確認しながら落ち着いて入力すれば大丈夫です。
もし不明な点があれば、税務署の職員や税理士に相談しましょう。
2年目以降の手続きは年末調整で

大変だった初年度の確定申告を終えると、2年目以降の手続きは格段に簡単になります。
給与所得者(会社員や公務員など)の方であれば、会社の年末調整で住宅ローン控除の手続きを完結させることができます。
これにより、わざわざ税務署へ足を運んだり、e-Taxで申告書を作成したりする必要がなくなります。
年末調整で必要になる書類
2年目以降の年末調整で必要となる書類は、基本的に以下の2点だけです。
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
一つ目の「住宅借入金等特別控除申告書」は、初年度の確定申告手続きが終わった後、その年の10月頃に税務署から送られてきます。
この書類は、2年目から控除期間が終了する年までの、残り年数分がまとめて一式送られてくるのが特徴です。
例えば、控除期間が13年であれば、残り12年分の申告書が一度に届きます。
毎年1枚ずつ使用していくことになるので、紛失しないように大切に保管しておく必要があります。
もし紛失してしまった場合は、税務署に連絡すれば再発行が可能です。
二つ目の「年末残高等証明書」は、住宅ローンを組んでいる金融機関から、毎年10月頃に自動的に送付されてきます。
これは、その年の年末時点でのローン残高がいくらになるかの見込み額が記載された証明書です。
年末調整での手続きの流れ
年末調整の時期(通常は11月~12月頃)になったら、勤務先の担当部署から年末調整の書類一式が配布されます。
その際に、上記の2つの書類を提出するだけで手続きは完了です。
具体的には、まず税務署から送られてきた「住宅借入金等特別控除申告書」の中から、該当する年分の用紙を1枚取り出します。
次に、金融機関から届いた「年末残高等証明書」に記載されている年末残高の金額を、申告書に転記します。
その他、氏名や住所、勤務先などの情報を記入し、捺印します。
この記入済みの申告書と、金融機関発行の残高証明書の原本を、勤務先に提出します。
これだけで、会社側が年末調整の計算に住宅ローン控除額を反映させてくれます。
控除による還付金は、通常12月か1月の給与に上乗せされる形で支払われることが多いです。
このように、2年目以降は手続きの負担が大幅に軽減されます。
ただし、自営業者や個人事業主の方など、年末調整の対象ではない方は、2年目以降も引き続き確定申告で手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
中古住宅やリフォームの場合の注意点
住宅ローン控除は、新築住宅だけでなく、中古住宅(既存住宅)の取得や、自宅のリフォーム(増改築等)を行った場合でも利用することができます。
ただし、これらの場合には新築住宅とは異なる特有の要件が加わるため、注意が必要です。
要件を満たしているかどうかを事前にしっかりと確認することが、控除を確実に受けるための鍵となります。
中古住宅の場合の主な要件
中古住宅で住宅ローン控除を受けるためには、前述した基本的な要件に加えて、建物の築年数や耐震性に関する条件をクリアする必要があります。
主な要件は以下の通りです。
- 建築後の経過年数要件:マンションなどの耐火建築物の場合は築25年以内、木造などの非耐火建築物の場合は築20年以内であること。
- 耐震基準適合要件:上記の築年数要件を満たさない場合でも、現行の耐震基準に適合していることが証明できれば対象となる。(例:耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)、既存住宅売買瑕疵保険への加入のいずれか)
つまり、古い建物であっても、耐震性が確保されていれば控除の対象となる道が開かれています。
耐震基準適合証明書などは、通常、物件の引き渡し前に取得する必要があります。
中古物件を検討する際には、これらの要件について不動産会社に確認し、必要であれば専門家によるインスペクション(建物状況調査)などを依頼すると良いでしょう。
なお、中古住宅の場合、控除期間は一律で10年間となります。
リフォームの場合の主な要件
リフォームで住宅ローン控除を利用する場合も、一定の条件を満たす大規模な工事が対象となります。
主な要件は以下の通りです。
- 自己が所有し、居住している家屋のリフォームであること。
- 一定の省エネ、バリアフリー、耐震、多世帯同居、耐久性向上などの特定の工事に該当すること。
- 工事費用が100万円を超えていること。
対象となる工事は法律で定められており、例えば、単に壁紙を張り替えるといった内装工事だけでは対象になりません。
窓を複層ガラスに交換する省エネ改修や、浴室に手すりを設置するバリアフリー改修、壁の補強などを行う耐震改修などが該当します。
リフォームで控除の適用を考えている場合は、計画段階でリフォーム会社にその旨を伝え、対象となる工事が含まれているか、また、証明書類(増改築等工事証明書など)を発行してもらえるかを確認しておくことが不可欠です。
中古住宅の購入と同時にリフォームを行う場合、条件を満たせば、住宅の取得費用とリフォーム費用を合算して住宅ローン控除を申請することも可能です。
制度が複雑に絡み合う部分でもあるため、不明な点は専門家に相談しながら進めることをお勧めします。
借り換えでも住宅ローン控除は使える?

住宅ローンを組んだ後、より金利の低いローンに乗り換える「借り換え」を検討する方も多いでしょう。
その際に、「借り換えをしたら、現在受けている住宅ローン控除はどうなってしまうのか?」という疑問が生じます。
結論から言うと、一定の要件を満たしていれば、住宅ローンを借り換えた後も、残りの控除期間について引き続き住宅ローン控除を受けることが可能です。
借り換え後も控除を継続するための要件
借り換えで控除を継続するためには、新しい住宅ローンが、当初の住宅ローンを返済するためのものであることが明確でなければなりません。
具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
- 新しい住宅ローンが、当初の住宅ローン等の返済のためであること。
- 新しい住宅ローンも、返済期間が10年以上であるなど、住宅ローン控除の基本的な適用要件を満たしていること。
この要件を満たしていれば、当初の居住年から起算した控除期間の満了まで、控除の適用が継続されます。
例えば、13年間の控除期間のうち、5年が経過した時点で借り換えを行った場合、残り8年間について引き続き控除が受けられます。
借り換え時の注意点
借り換えを行う際には、いくつか注意すべき点があります。
1. 控除額の計算基準
借り換え後の控除額の計算は、借り換え直前の当初のローン残高と、新しいローンの借入額のうち、いずれか少ない方の金額が基準となります。
例えば、借り換え前の残高が2,500万円で、諸費用なども含めて2,600万円を新たに借り入れた場合、控除の対象となるのは2,500万円までです。
借り換えによって借入額が増えたとしても、控除額が増えるわけではない点に注意しましょう。
2. 年末調整での手続き
借り換えを行った場合、その年の年末調整の手続きが少し変わります。
通常の書類に加えて、新しい金融機関が発行する「年末残高等証明書」が必要になります。
場合によっては、借り換え前の金融機関と借り換え後の金融機関、両方の残高証明書が必要になるケースもあるため、勤務先の指示に従って書類を準備しましょう。
3. 控除期間の延長はない
借り換えによって、控除期間がリセットされたり、延長されたりすることはありません。
あくまで、最初に控除の適用を受けた年からカウントした期間が満了するまでとなります。
金利の低下は総返済額を減らす大きなチャンスですが、借り換えには手数料などの諸費用もかかります。
住宅ローン控除の継続適用の可否も含め、諸費用と金利低下のメリットを総合的に比較検討し、慎重に判断することが大切です。
金融機関の借り換え相談窓口などでシミュレーションをしてもらうと良いでしょう。
総括:住宅ローン控除とは賢く活用すべき制度
ここまで、住宅ローン控除とは何か、その全体像を多角的に解説してきました。
この制度は、住宅ローンを利用する多くの人にとって、家計の負担を直接的に軽減してくれる非常に価値のある税制優遇措置です。
制度の仕組みは、毎年の税制改正によって変化するため、少し複雑に感じられる部分もあったかもしれません。
しかし、その要点を押さえ、ご自身の状況に合わせた正しい知識を持つことで、その恩恵を最大限に享受することができます。
改めて、この記事で解説してきた重要なポイントを振り返ってみましょう。
住宅ローン控除とは、単なる節税テクニックではなく、国が国民の良質な住まいの形成を後押しするための重要な政策です。
だからこそ、省エネ性能の高い住宅ほど優遇されるといった、時代の要請を反映した仕組みになっています。
これから住宅を購入する方は、この制度を深く理解し、ご自身のライフプランや資金計画に賢く組み込んでいくことが求められます。
手続きには手間がかかる部分もありますが、それを乗り越えた先には、十数年にわたる大きな経済的メリットが待っています。
もし不明な点や判断に迷うことがあれば、一人で抱え込まずに、税務署や税理士、金融機関、不動産会社の担当者といった専門家に相談することも大切です。
ぜひ、この住宅ローン控除という制度を味方につけて、より豊かで安心なマイホームでの生活を実現してください。
fa-file-powerpoint-o
この記事のまとめ
- 住宅ローン控除とは年末ローン残高の0.7%が税金から控除される制度
- 正式名称は住宅借入金等特別控除
- 控除期間は新築で最長13年、中古で10年
- 2025年までは住宅の環境性能で借入限度額が変わる
- 省エネ基準を満たさない新築住宅は2024年から原則対象外
- 適用には年収2,000万円以下、床面積50㎡以上などの条件がある
- 控除額は自身の納税額が上限となる
- 所得税で引ききれない分は住民税からも一部控除される
- 住民税からの控除上限は課税所得の5%または9.75万円
- 初年度は必ず確定申告が必要
- 会社員は2年目以降、年末調整で手続きが可能
- 中古住宅は築年数や耐震基準の要件を満たす必要がある
- 100万円超の特定のリフォームも控除の対象になる
- 条件を満たせばローンを借り換えても控除は継続できる
- 制度を正しく理解し計画的に活用することが重要